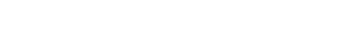令和5年 一般会計・特別会計決算特別委員会(2023.10.26)
<福祉局関係>【日比たけまさ委員】
令和4年度決算に関する報告書の84ページ、重層的支援体制整備事業交付金に関連して伺う。
現在の地域社会は、少子・高齢化や核家族化の進行を背景につながりが希薄化し、支え合いの機能も低下していると言われる一方で、子育てと介護を同時に抱えるダブルケアや、ひきこもり状態の中高年の子供の生活を高齢の親が支える8050問題など、個人や世帯が抱える課題は複合化、多様化している。
こうした中、地域住民や多様な主体が参画し、支え合いながら地域をつくる地域共生社会の実現を目指して、市町村における重層的支援体制整備事業の実施に期待が高まっている。
そこで、制度開始から2年が経過した昨年度までの市町村における実施状況と、それに対する評価について伺う。
【地域福祉課担当課長】
はじめに、実施状況であるが、重層的支援体制整備事業が開始された2021年度には5市、2022年度には10市町、さらに今年度は14市町において事業が実施をされている。
次に、市町村の実施状況に対する評価であるが、本県では、福祉・保健・医療分野全体の方向性を示す、あいち保健医療福祉ビジョンにおいて、2026年度までに20市町村で本事業を実施することを目標としており、この目標に向かって順調に進捗していると考える。
【日比たけまさ委員】
答弁では順調に推移し、増加しているということであるが、まだ多くの市町村が実施に至っておらず、引き続き働きかけが必要ではないかと考える。
さらに、既に事業を開始している市町村においても、住民への普及啓発や、多様な機関のさらなる連携強化など、事業実施に当たって様々な課題を抱えていると考える。
そこで、県として、市町村における重層的支援体制整備事業の円滑な実施に向け、どのような取組を実施しているのか伺う。
【地域福祉課担当課長】
本県では、昨年9月に社会福祉法人愛知県社会福祉協議会と協働し、市町村や本事業の主な連携先である市町村社会福祉協議会の職員を対象とした研修会を開催した。この研修会では、重層的支援体制整備の必要性を分かりやすく伝える講義のほか、シンポジウム形式で先進自治体の事例を紹介するなど、市町村における取組の促進を図った。今年度は12月に開催を予定しており、講義や事例紹介に加え、相互の意見交換が進むようグループワークを実施することとしている。
県としては、引き続きこうした研修を通じて、未実施市町村へ実施に向けた働きかけを行うとともに、事業実施上の課題の共有を図るなど、市町村における取組を支援していく。
【日比たけまさ委員】
国はこの重層的支援体制整備事業を、市町村において、全ての地域住民を対象とする包括的支援の体制整備を行う事業と位置づけ、体制を支えるためのアウトリーチや多機関協働の機能を強化していくとしている。
生活を送る中で直面する困難、生きづらさの多様性・複雑性を抱える住民に対して、本人に寄り添って伴走する支援体制を市町村が着実に構築できるように、県としてもしっかりとサポートを行うよう要望する。
次に、令和4年度決算に関する報告書の86ページ、福祉・介護人材確保対策費について伺う。
団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025年を控え、介護需要が高まる中、介護に従事する人材の確保を進めるためには、幅広い年代に向けた取組が必要と考える。
そこで、県は、どのように取り組んでいるのか伺う。
【高齢福祉課担当課長】
幅広い年代に向けた取組として、介護に関する専門的な知識や技術を持っていない方の不安を払拭し、多様な人材の参入を促進するため、4日間の介護に関する基本的な研修を受講した方に、あいち介護サポーターとして登録をしてもらい、派遣を希望する介護事業所とのマッチングを行う、あいち介護サポーターバンク運営事業を2016年度から実施している。
その登録状況は、2020年度が299人、2021年度が382人、2022年度が390人である。
次に、介護事業所とのマッチング数であるが、2020年度が60件、2021年度が132件、2022年度が132件である。マッチング成立者のうち約7割は50歳以上であり、中高年齢者の介護分野の参入に寄与していると考えている。
また、若い世代においては、核家族化の進行により高齢者と身近に接する機会が少ない、また、介護職における一面的なマイナスイメージが浸透しているといった状況があることから、介護職への正しい理解の醸成とイメージアップを図るためのリーフレットを、小学生、中学生、高校生向けに作成し、県内の各学校に配布をしている。
今後もこうした取組を進め、多様な年齢層への働きかけを行い、介護従事者の確保に努めていく。
【日比たけまさ委員】
50代以上が積極的に登録している、若い人への普及啓発を行っているとの答弁であるが、今後も少子化が進行する中で、介護人材を確保するためには、外国人介護人材を受け入れて活用することが必要だと考える。
しかし、受入れを検討している事業所には、受入れに当たっての流れや必要な準備が分からないといった不安があり、また、実際に受け入れた事業所は、言葉の問題などから、外国人介護人材に対する効果的な指導方法が分からないといった不安を抱えている。
外国人介護人材の受入れを進めていくためには、受入れ前や受入れ後に、事業所が抱えるこうした不安に対する支援が必要であると考えるが、県としてどのように取り組んでいるのか伺う。
【高齢福祉課担当課長】
本県では、外国人介護人材の受入れを検討している介護事業者に対して、その在留資格に関する制度や受入れ後の教育、生活支援方法、先進事例等を伝える外国人介護人材受入セミナーを2020年度から実施している。2022年度は95事業所、117人に参加をしてもらった。
また、2022年度からは、実際に受入れを行った事業所の指導担当職員を対象とした、グループワークによる効果的な指導方法等を学ぶための指導担当職員特化型セミナーを開始した。このセミナーは、昨年度は定員を上回る申込みがあり、定員を拡大して、31事業所、38人に参加をしてもらった。
今後も引き続き、こうした介護人材の受入れ支援をしっかりと進めていきたいと考えている。
【日比たけまさ委員】
福井県では、外国人介護人材の確保を促進するために、県と県社会福祉協議会が連携して、タイからの介護人材の継続的な受入れを目指して、現地で日本語や介護の教育を行うなど、介護人材の育成に取り組んでいる。
外国人介護人材の受入れに対する状況が本県とは異なることは承知しているが、介護の仕事はやはりコミュニケーション能力が極めて重要となる中で、コミュニケーションが取れるまでに時間がかかってしまう一方、慣れた頃には期限がきてしまうといった事業者からの声も聞いているため、外国人介護人材の活用に向けて、こうした声をさらに施策に反映するよう要望する。
次に、令和4年度決算に関する報告書の96ページ、保育士・保育所支援センター費について伺う。
本県では、2020年3月に策定したあいちはぐみんプラン2020-2024において、2024年度までに常勤換算で3万人の保育士確保を目標に掲げている。こうした中、保育士・保育所支援センターでは、専任のコーディネーターを配置して保育士確保を図ったとあるが、取組の状況について伺う。また、現在の本県における保育士数についても伺う。
【子育て支援課担当課長】
2022年度に、保育士・保育所支援センターでは、専任のコーディネーターによる再就職に関する相談や求人と求職のマッチングなどを行うとともに、潜在保育士向けの研修を7回、就職フェアを2回開催するなど、潜在保育士の再就職支援に取り組み、125人の保育士が県内の保育所等に採用された。
こうした取組などにより、本年4月1日現在の保育士数は、常勤換算で2万9,965人となっており、はぐみんプラン策定当時の2019年の2万6,887人と比較すると、約3,000人増加している。
【日比たけまさ委員】
次に、令和4年度決算に関する報告書の97ページから98ページにかけての保育補助者雇上強化事業費補助金及び保育体制強化事業費補助金について伺う。
先ほどの答弁では、計画上は順調に保育士数が増加しているとのことであったが、実際の保育現場では、痛ましい事故や不適切保育が全国的に明るみになっている。保育士の確保のためには、保育士の数だけではなく労働環境の改善も重要であると考える。
保育士の勤務環境改善や保育士の業務負担の軽減を目的として、この保育補助者雇上強化事業費補助金や保育体制強化事業費補助金を活用して、保育補助者や保育支援者の雇用を支援しているということであるが、具体的な事業内容はどのようなものか。
【子育て支援課担当課長】
保育補助者雇上強化事業費補助金については、保育士資格は持っていないものの、保育に関する研修を受講するなどにより、一定の知識を持ち、保育士と共に子供の着替えや食事の世話をする保育補助者の雇用に係る費用を助成するものであり、2022年度は19市町に対して、108施設、255人分の保育補助者の人件費の補助を行った。
制度の開始は2017年であり、実績としては当時8施設、14人であった。当時と比較すると、本事業を活用する施設は増加傾向である。
次に、保育体制強化事業費補助金については、清掃やおもちゃの消毒、園外活動の見守りなど、保育の周辺業務を行う保育支援者の雇用に係る費用を補助するものであり、2022年度は26市町村に対して454施設、821人分の保育支援者の人件費の補助を行った。
この制度が開始した2018年度の実績は32施設、41人であり、この制度も年々増加している。
【日比たけまさ委員】
次に、令和4年度決算に関する報告書の96ページから97ページの、子育て支援関係職員研修費について伺う。
子供の適切な支援に向け、就学前の早期療育へのつなぎが大切であると考える。そのためには、保育士等の発達障害に関する理解が重要であるが、保育士に対する発達障害に関する研修はどのようであったか、また、研修実施に当たっての課題とその解決に向け。今後どのように取り組んでいくのか伺う。
【子育て支援課担当課長】
保育士に対する発達障害に関する研修としては、保育士等キャリアアップ研修の中に、障害児保育に関する分野がある。障害児保育に関する理解を深めて、保育の専門性に基づき、一人一人の子供の発達の状況に応じた保育を学んでもらう内容となっており、2022年度は694人が受講した。なお、保育士等キャリアアップ研修全体では4,900人が受講し、研修方法は時間や場所の制約を受けないオンライン形式としている。
また、課題としては、例年受講希望者が多く、2022年度は受講定員3,890人に対して8,895人が受講を希望した。このため、今年度からは、受講定員を3,890人から9,000人に2倍以上の増員をし、希望する全ての方が受講できるよう体制整備を図った。
障害児保育の分野についても、受講定員を570人から1,350人に増員している。引き続き、保育士の資質向上が図られるよう、研修事業に取り組んでいく。
【日比たけまさ委員】
保育人材の確保や業務負担の軽減、資質の向上について、様々な取組を実施していることが確認できたが、保育現場にゆとりを生み出す施策は、さらに充実が必要である。
政府は6月13日に閣議決定したこども未来戦略方針に、職員配置基準について、1歳児は6人から5人、4歳・5歳児は30人から25人に改善すると記載をし、基準より手厚い配置をする園への運営費を加算する方向で検討を進めている。本県は独自に、1歳児保育実施費を行っていると思うが、ほかの年齢に拡大するなど、さらなる充実を図るよう要望する。
最後に、子育て支援関係職員研修費に関して、一点質問する。
放課後児童クラブの職員に関する研修について、その目的と実施内容について伺う。また、放課後児童クラブの人材確保に当たっての課題と、課題解決に向けどのような取組を行っているのか伺う。
【子育て支援課担当課長】
はじめに、放課後児童支援員研修についてであるが、研修の目的は、放課後児童クラブにおいて配置が義務づけられている、子供の育成支援に当たる放課後児童支援員を養成するものである。実施内容は、放課後児童支援員として必要となる児童の基本的生活習慣の習得の援助、自立に向けた支援等に必要な知識及び技能を習得するものであり、放課後児童クラブの理解や放課後児童クラブにおける子供の育成支援など、1日6時間の講義及び演習を4日にわたり実施するものである。なお、2022年度は12回実施し、785人が受講した。
次に、放課後児童支援員キャリアアップ研修についてであるが、研修の目的は、放課後児童支援員等に対して必要な知識及び技術の習得並びに課題や事例を共有するための研修を行うことにより、資質の向上を図るものである。実施内容は、発達障害児など配慮を必要とする子供への支援や保護者との連携支援など、子供の育成支援に関連して、1テーマ当たり3時間の講義及び演習を行うものであり、2022年度は10回実施し、延べ1,166人が受講した。
最後に、放課後児童クラブの人材確保の課題と取組についてであるが、決算に関する報告書には記載がないが、研修事業と同じく、決算に関する報告書の96ページの子育て支援関係職員研修費の中で、放課後児童クラブ人材確保事業を行っている。
放課後児童クラブでは、小学校の夏休みや冬休み等の長期休業期間に利用ニーズが高まることから、長期休業期間の人材確保が課題となっている。このため、指定保育士養成施設の学生を対象に、放課後児童クラブの現状や魅力、やりがいについてセミナーを開催し、特に利用ニーズが高まる長期休業期間の就労の働きかけを行った。
なお、2022年度は、愛知県立大学、日本福祉大学、岡崎女子大学及び中部大学の4大学において実施し、171人の学生が受講した。
【日比たけまさ委員】
学童保育も保育士と同じで、人材の確保や業務負担の軽減、資質向上に向けて、様々な施策を展開していることは確認できたが、やはり現場にゆとりがないというのが現状だと思う。
対策の一つとして展開している放課後児童支援員等に係る処遇改善事業について、県から市町村に対し働きかけを行っていることは承知しているが、実際には一部の市町村しか実施していない。より多くの市町村が実施するよう、さらに県として働きかけを行うよう要望する。