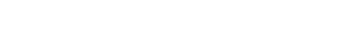令和5年 警察委員会(2023.10.12)
【日比たけまさ委員】
危険ドラッグ事犯及び大麻事犯の情勢、対策について伺う。
先月末、2015年に一度ゼロとなっていた危険ドラッグの販売店舗数が、本年8月末時点で全国に約300店舗あることが厚生労働省の調査で分かったという報道があった。
危険ドラッグの販売動向については、私自身2012年12月定例議会の本会議及び2015年6月定例議会の警察委員会で質問している。
2012年は警察本部長から、2012年7月と11月に県内の脱法ハーブ販売店に対し、県と合同で立入りを行い、販売実態の調査と販売自粛要請を実施、県内の販売店は最盛期で約40店舗あったものが約20店舗まで減少しているとの答弁があった。
また、2015年には組織犯罪対策局長から、危険ドラッグを販売する店舗については、2014年7月時点で県内に18店舗を確認していたが、同年7月15日に愛知県警察危険ドラッグ総合対策本部を設け、強力な取締りを進め、薬事法、薬物の乱用の防止に関する条例などにより販売店9店舗、経営者など28人を検挙した。また、県や東海北陸厚生局の麻薬取締部との合同で立入りを行い、当時営業していた販売店に対し、危険ドラッグの販売を中止するよう指導するなど、2014年10月末までに18店舗全てを廃業、閉店させ、それ以降、愛知県で危険ドラッグに関する事象は激減しているとの答弁を得ていた。
その後も危険ドラッグについてほとんど耳にしなくなった中での今回の報道は、正直ショックを受けた。危険ドラッグは、合成大麻などの名称で売られているとの報道もあり、若者の大麻乱用と併せて大変気がかりである。
そこで、危険ドラッグ及び大麻事犯の現状について伺う。
【組織犯罪対策課長】
初めに、危険ドラッグ事犯の検挙人員については、ピーク時の平成27年には84人であったものがそれ以降は減少し、令和3年には3人まで減少した。しかし、昨年からは増加傾向となっており、令和4年は12人、令和5年は8月末現在で14人となっている。
また、最近の危険ドラッグは、以前流通していた植物片や粉状タイプのものではなく、大麻類似成分を含んだ、電子たばこのように吸う液体タイプが多数を占めている。
次に、大麻事犯であるが、近年、検挙人員は増加傾向にあり、令和4年は過去最多の410人となった。令和5年は8月末現在で307人となり、覚醒剤事犯の295人を上回っている。過去、大麻事犯が覚醒剤事犯を上回ったことはなく、大麻事犯の増加を示す結果となっている。
また、大麻事犯における検挙人員の約77パーセントは、10代、20代の若年層であり、若年層の大麻蔓延を示す結果となっている。危険ドラッグ、大麻ともに、インターネットやSNSの発達により容易に入手できるようになったことが増加の原因と考えている。また、大麻は健康への被害が少ないといった誤った認識が広がっていることなども増加の一因である。
【日比たけまさ委員】
答弁の内容を確認すると、今年度の現時点での大麻事犯の検挙人員が覚醒剤事犯を上回るという、これまでにない状況が発生していること、若年層に対する大麻蔓延がかなり深刻であること、加えて危険ドラッグも増加傾向とのことである。薬物は使用年齢が早ければ早いほど依存症になりやすく、また治療も困難になってしまうとも言われている。当然のことながら様々な対策の強化が求められる。
そこで、危険ドラッグ及び大麻事犯の取締り状況及び方策について伺う。
【組織犯罪対策課長】
薬物事犯については、末端乱用者に対する取締りだけではなく、供給側に対する捜査が重要である。
まず、危険ドラッグであるが、最近の状況から、愛知県内にも危険ドラッグ販売店舗が存在していると考えており、東海北陸厚生局麻薬取締部等の関係機関と連携して、県内の実態把握及び取締りを推進している。
次に、大麻事犯については、末端乱用者の検挙等を端緒として、供給側を営利目的の大麻密輸入事件、大麻栽培事件等で検挙しており、一例として、令和5年5月に末端価格約18億円相当の乾燥大麻を密輸入した被疑者を検挙し、同年7月には、全国に乾燥大麻を供給していた福島県内の大麻栽培工場を摘発し、関係被疑者4人を検挙して、大麻草約250株を押収している。また、最近ではSNS利用による大麻の密売事件についても検挙している。
引き続き末端乱用者だけではなく、供給側の密輸入、それから密売組織に対する捜査を強力に推進していきたい。
【日比たけまさ委員】
8月末、大麻取締法違反の罪に問われた俳優の永山絢斗被告の初公判が開かれ、その場で、永山絢斗被告が大麻を初めて使用したのは中学2年生のときであったという衝撃的な事実が明らかになった。また、最近では、日本大学アメリカンフットボール部の学生寮で大麻と覚醒剤が見つかった事件も大変大きな話題となっている。
こうした中、政府は今月20日招集の臨時国会で、てんかんの治療薬など、大麻由来の成分を使った医療用大麻を使えるようにする一方、乱用を防ぐため、罰則つきの使用罪を新たに設けるといった大麻取締法の改正案を提出する方針であるとの報道がある。
私が懸念しているのは、若者に大麻解禁と誤った認識が広まらないかという点である。若年層に対する広報啓発の重要性が一層増していることは間違いない。
そこで、若年層に大麻をはじめとした薬物乱用が増加して問題となっているが、広報啓発はどのように行っていくのか。
【少年課長】
県警察としては、教育委員会や学校と連携し、警察官が小中高等学校を訪問して薬物乱用防止教室を開催し、DVDの視聴、薬物標本等の閲覧、グループワークを取り入れた講話等を通じて、大麻をはじめとする薬物の危険性、有害性、違法性を正確に伝え、児童生徒の心に響く啓発に努めており、令和4年は合計556校、約9万2,000人の児童生徒を対象に実施した。
また、薬物の危険性について、多くの若者に関心を持ってもらうために作成した漫画や動画を県警察公式SNSなどへ掲載し、注意喚起を図っている。
さらに、大学運動部員による薬物乱用がクローズアップされたことから、これまでに愛知県内の大学運動部員等に対する薬物乱用防止講話を実施しており、今後は社会人クラブチームに対しても講話を実施する予定である。
県警察としては、引き続き関係機関と連携の上、特に若年層を重点に薬物の危険性、有害性、違法性に関する広報啓発活動を推進して、大麻をはじめとした薬物乱用の未然防止に努める。
【日比たけまさ委員】
近年、大麻をはじめとした薬物乱用問題は本県に限らず全国的な問題で、今まさに対策の強化が求められている。答弁でも様々な取組を実施していることが分かり、先日の本会議の一般質問では、県側の取組も明らかになった。ぜひ関係者が一丸となって若者の薬物乱用防止により一層力を入れることを要望する。