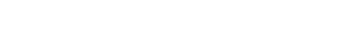令和5年 一般会計・特別会計決算特別委員会(2023.11.15)
<経済産業局関係>【日比たけまさ委員】
令和4年度決算に関する報告書175ページの外国企業誘致促進事業費について伺う。
報告書にはINVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUM、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会等と連携し、外国企業の誘致、進出、定着支援を行ったと記載されている。具体的にどのような活動を行ったのか。
【産業立地通商課担当課長】
INVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUMは、県と名古屋市におけるイノベーションの創出や産業の活性化、雇用拡大を図るため、地域一体となって外国企業等の進出及び定着を促進することを目的として、愛知県、名古屋市、公益財団法人名古屋産業振興公社を構成員として令和4年3月に設立された。
同コンソーシアムでは、令和4年度は、既に県内に進出済みの外国企業の定着を促進する事業として、外国企業9社の共同ブースによるメッセナゴヤへの出展支援や、県内企業との人脈構築を目的としたネットワーク懇談会を開催した。
次に、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会は、名古屋を中心として半径100キロメートルの圏域内に世界から優れた企業、人材等を呼び込むことを目的として、グレーター・ナゴヤという統一ブランドの下、愛知県や岐阜県、三重県などの行政、産業界、大学等が一体となって当地域への外国企業の誘致や海外への情報発信等を行う協議会である。
同協議会では、令和4年度は外国企業の会社の設立や、人材募集時に必要となる経費の一部を助成する拠点立ち上げ支援のほか、対日投資に向けた外国企業の発掘等を目的としたドイツへのミッション派遣、また、グレーター・ナゴヤ地域内の企業との企業間交流イベントとして、ベトナムやタイ、英国企業とのビジネスマッチングを実施するなど、地域一体となった誘致活動を行った。これらの取組を通じ、昨年度は、本県へ7社の外国企業を誘致した。
【日比たけまさ委員】
外国企業をさらに誘致するため、今後、どのような取組を実施していくのか。
【産業立地通商課担当課長】
INVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUMにおいては、昨年度は、県内展示会への出展支援やネットワーク構築支援といった本県に進出済みの外国企業に対する定着促進支援がメインであったが、今年度からは、構成員として国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学にも参画してもらい、外国企業の本県への進出を促進する事業にも取り組んでいる。
具体的には、外国企業向けの相談窓口の設置のほか、外国企業向けに当地域のビジネス環境の強みなどをPRするセミナー・オンラインマッチングの実施、さらには、本県への進出を検討している外国企業4社を選定して行う伴走支援や、来年3月に県内で開催されるスマートマニュファクチャリングサミットバイグローバルインダストリー(SMART MANUFACTURING SUMMIT BY GLOBAL INDUSTRIE)に合わせた外国企業の招聘といったアクセラレーションプログラムを実施していく。
また、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会においても、対日投資促進事業や国際経済交流事業はもとより、今年度は県内に進出済みの外国企業へのヒアリング調査を実施し、外国企業誘致の施策立案を検討することとしている。
こうした新たな取組も進めることで、1社でも多くの外国企業の誘致につなげたい。
【日比たけまさ委員】
大村秀章知事は日頃、国内外から、人、物、金、情報を愛知に呼び込むと発言している中、現在の円安状況は、外資系企業の日本への新規投資を促す絶好のチャンスである。インバウンド促進が海外から人を、対日投資が海外から企業をそれぞれ日本に取り込む政策であり、安い日本が経済成長を実現するために不可欠の両輪として注力すべき戦略だと思う。そして、海外から技術や資金を呼び込むことが愛知でのイノベーション創出にもつながるため、今こそ積極的な海外企業の誘致に取り組んでもらうよう要望する。
続いて、令和4年度決算に関する報告書183ページの再生可能エネルギー実現可能性検討調査費について、報告書には、本県における再生可能エネルギーの導入拡大に向け、実態の把握や課題の整理、実現可能性の検討に必要な調査を実施したと記載されているが、この事業の内容及び成果について伺う。
【産業科学技術課担当課長】
この調査は、太陽光、陸上風力、洋上風力、バイオマス、水力及び地熱といった再生可能エネルギー全般について、国内外の現状、自然面、社会経済面の課題、導入のポテンシャルなどについていろいろ整理をした調査になっている。
調査に当たっては、文献やデータの整理だけでなく、いろいろなアンケートも行った結果、太陽光発電及び洋上風力発電の二つの伸び代が大きいとわかった。太陽光発電は、民間主導でできると思うが、特に愛知県の場合は比較的大規模な導入ができる工場や倉庫での導入のポテンシャルが全国で最も大きいとの調査結果がある。
洋上風力発電は、欧米や中国が進んでいるが、日本でも2019年に再エネ海域利用法ができるなど、機運が高まっている中で、本県の場合は、渥美外海、具体的には田原市、豊橋市沖の風がよく、洋上風力発電のポテンシャルが高く有望である。さらに風車には、この地域の製造業で作られる部品が多数入っている。風車自体は、中国と欧米に押さえられている状況ではあるが、比較的参入しやすい。このことを踏まえ、もう少し踏み込んだ調査を本事業で行った。この地域の風や波で稼働率がどれくらいか、波が高いと工事もできないため、工事がどれぐらいやりやすいかといったシミュレーションまで行った。
【日比たけまさ委員】
県は、今年3月、国、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が進める洋上風力発電の低コスト化プロジェクトの候補海域に田原市、豊橋市沖を応募し、10月3日、洋上風力発電浮体式実証の候補海域として田原市、豊橋市沖が選定されたと発表した。
そこで、再生可能エネルギー実現可能性検討調査と今回の候補海域選定の発表との関連について伺う。
【産業科学技術課担当課長】
今回の調査は、いわゆる再生可能エネルギーのポテンシャルを調べるものだが、2019年の再エネ海域利用法でこれから洋上風力発電を広げていく中では、漁業者の理解が要ると書かれている。今回の調査と並行して、その可能性について、県漁連に打診を行ったが、渥美沖はシラス、イワシ及びクルマエビ等の操業が盛んであるため、沿岸は難しいとの話であった。
昨年の9月頃に、国のグリーンイノベーション基金で、深さ100メートル程度の海で風車を建てる浮体式の実用化に向けた実証実験を総額850億円で2か所程度実施する話が持ち上がり、そのことを踏まえて改めて県漁連に打診したところ、浮体式であれば沖合15キロメートル程度で漁が比較的少ないエリアであり、期間限定の実証実験であれば、公募に手を挙げてもよいといってもらえたため、候補海域として手を挙げ、10月3日に選ばれた。
今のところ、まだ四つの海域が選ばれただけの状況であり、この先、2か所程度に絞られるまで、できれば意欲のある事業者に手を挙げてもらい、この地域が選ばれるようにしていきたい。
【日比たけまさ委員】
今回の候補海域選定を受けて、今後、国、NEDOが事業者の公募を開始して、最終的な採択は2か所程度と、事業者が事業を開始するのは2024年春頃の見通しである。今回、田原市、豊橋市沖で実証事業が行われるよう、ぜひ県として応募を検討する事業者に対しての積極的な協力を要望する。
<労働局関係>
【日比たけまさ委員】
令和4年度決算に関する報告書191ページの中小企業テレワーク導入支援事業費について、県では、テレワークの導入や定着に必要な支援を行う拠点として、令和3年度にあいちテレワークサポートセンターを開設した。令和3年度は、コロナ禍による人流抑制と重なって企業においてテレワークの導入が一定程度進んだと思うが、経済活動が回復した令和4年度の利用状況について、令和3年度の実績を踏まえた新たな取組があれば、それも含めてどのような実績となったのか。
【労働福祉課担当課長】
あいちテレワークサポートセンターは、令和3年4月28日に開設した。同年8月18日にはテレワーク体験や見学が可能なあいちテレワーク・モデルオフィスを併設している。センターは、テレワークに関する相談対応、モデルオフィスの運営に加えて、企業へのアドバイザー派遣など、ワンストップで支援する。
利用実績は、開設年度の令和3年度の相談件数が1,310件、モデルオフィス利用者数が1,417人、アドバイザー派遣企業数が42社の実績に対して、令和4年度は相談件数が1,426件、モデルオフィス利用者数が2,374人、アドバイザー派遣企業数が41社である。
令和3年度は年度途中のセンター開設になるため単純比較はできないが、1か月単位の利用状況で見ると、いずれの取組についても前年度と同程度の利用実績となっている。
センターでは、テレワークに関する様々な悩み、課題に対応しているが、利用する企業からは、テレワークツールの導入に関して、コストの問題や自社のシステムとの連携の不具合が生じることから、テレワークツールを本格導入する前に試してみたいとの要望をもらった。このため、令和4年度はテレワークツールを搭載したパソコン機器を無料で貸し出し、専門家による指導、併せて実際の職場環境でテレワークを試してもらう取組を新たに開始した。
この実績は、支援予定10社を上回る13社の企業に利用してもらった。利用した企業からは、実際に機器を使用することができて機器導入の検討に役立ったと聞いており、本格的なテレワーク導入に向けた効果的な支援になった。
今年5月から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行して日常的な行動規制が緩和される中で、一部の企業でコミュニケーションの難しさからテレワークを縮小する動きもある。しかし、今年度のセンター実績については、10月末現在で相談件数が1,078件、モデルオフィスの利用者数が1,685人と昨年度の同時期と比べても上回る実績を達成している。
県としては、今後とも、センターが実施する各種支援メニューを通じて、企業の多様なニーズに応えることにより、県内企業におけるテレワークの導入及び定着をしっかりと進めていきたい。
【日比たけまさ委員】
8月16日の日本経済新聞にもテレワーク実施率が22パーセントに低下し、新型コロナウイルス感染症の5類移行で減少する一方、職場に出社する人が増えたという記事があった。その一方で、テレワークのメリットとして、ペーパーレス化、デジタル化を促進、ワーク・ライフ・バランスが保ちやすい、人材確保につながる、事業継続性の確保などが広く認識され、現在は、オフィスワークと自宅やシェアオフィスなどで働くリモートワークを組み合わせ、従業員が柔軟に働くことができる制度、いわゆるハイブリッドワークが広がっていると言われている。こうした流れを鑑みると、今後もテレワークの導入と継続は必須と考えられるため、引き続きの対応をお願いしたい。
最後に、令和4年度決算に関する報告書193ページの外国人雇用促進事業費について伺う。
最近、若者たちの間でバ畜という言葉が広がっている。バ畜とは、社畜とバイトを組み合わせた造語で、社畜は、会社のためにがむしゃらに働かされる人を指すものであり、バ畜は、そのバイト版を意味する。背景には、慢性的な労働力不足に加え、消費者が安く質の高いサービスを求める社会の中、低賃金のアルバイトなどに過重労働をさせざるを得ない状況が発生していることが挙げられ、解消に向けては、働きやすい環境の整備、そして、多様な人が働くことができる環境の整備が必要である。
当該事業は、その一翼を担う事業であると考えるが、どのような取組であるのか。
【就業促進課担当課長】
外国人雇用促進事業では、就業・就労の制限のない定住外国人の雇用促進や就職支援のため県内企業向けの雇用相談及び定住外国人向け就職相談を行う相談窓口の運営や、市町村等への出張相談を実施した。
相談窓口では、外国人の雇用を検討する企業に対する外国人の受入れ体制整備など雇用に関する助言や、定住外国人求職者に対する仕事の探し方や就職活動の進め方などについて助言や情報提供等を行った。
また、企業に対して、定住外国人の円滑な雇用が図れるよう、社会保険労務士や行政書士等の専門家を活用し、社内規程などの体制整備等や採用手続に関する助言から雇用後の職場定着までを継続的にフォローするとともに、定住外国人に対しては日本語能力の向上など、就職に必要なスキルを身につけるための伴走型支援を行った。
【日比たけまさ委員】
この事業の令和4年度の実績はどうであったのか。
また、人手不足業界の一つに介護業界が挙げられ、私は、先日、福祉医療費の決算審査の際に、この介護人材の確保を目的とした外国人介護人材の受入れに対する支援について聞いた。
今回は、労働局における介護業界での外国人材の確保や育成の状況についても伺う。
【就業促進課担当課長】
令和4年度の相談窓口での利用実績だが、企業から134件、定住外国人から164件となっており、いずれも前年度の件数を上回っている。
伴走型支援は、定住外国人の雇用を希望する企業6社と就職を希望する定住外国人14人に対して支援を実施した。そのうち、2人が伴走型支援を実施した企業に就職しており、うち1人は、介護事業所に雇用されている。なお、本事業とは別に介護分野外国人就業支援事業として定住外国人を対象とした雇用型訓練と就職支援を行っており、令和4年度は訓練修了者23人のうち、22人が介護事業所に就職している。
【日比たけまさ委員】
少子化が進行し人材確保がより困難になる中、介護人材の確保には外国人介護人材の受入れ、活用が必須であるため、引き続き支援の充実を要望する。
全体の話として、この外国人労働者が必要とする情報提供や無料で受けられる労働相談、弁護士による法律相談などを母国語で受けられる体制の拡充、また、外国人労働者を雇用する事業主には就労環境整備のための外国人雇用管理指針が徹底されるよう、働きかけを要望する。
<農業水産局関係>
【日比たけまさ委員】
令和4年度決算に関する報告書210ページの農作物鳥獣被害防止対策費について伺う。
丹羽洋章委員の質問への答弁でも農作物の鳥獣被害が非常に深刻だと理解した。
そこで、県が主に行っている取組で、被害防止対策推進費について伺う。
この報告書には新規開発された技術について現地実証を行ったという記載があるが、具体的にはどのような取組を行ったのか。
【野生イノシシ対策室長】
報告書にある新規開発された技術の現地実証とは、鳥獣被害で困っている地域の農業者からの相談に対して、該当する地域を所管する農林水産事務所の農業改良普及課と長久手市にある農業総合試験場が連携し、国や本県及び他県の研究機関などで開発された鳥獣被害防止対策技術を現地に導入して、その効果を検証する取組である。
2022年度は、県内5つの農業改良普及課において7つの技術実証を行った。その一例として、本県で最も被害額の大きいカラスに関する現地実証について説明すると、岡崎市内のブドウ園のカラス対策として、ブドウの棚上に2.5メートル間隔で直径0.5ミリメートルのステンレスワイヤーを設置したエリアと、同じ太さの黒色のテグスを設置したエリアを設けて、カラスの侵入防止効果及び資材の経済性について比較調査を行った。その結果、どちらのエリアもカラスの侵入が確認されず、侵入防止効果に有意差がなかったことから、単価の安いテグスの方が費用対効果が高く、経済性に優れていることが確認できた。
こうした取組結果については各農業改良普及課で情報共有をするとともに、効果的な鳥獣被害対策として活用してもらえるよう、農業者が参加する研修会等で関係機関を通じて情報提供を行っている。
【日比たけまさ委員】
鳥獣被害対策というのは、捕獲による個体数の管理と侵入防止対策、さらには、生息環境管理の3本柱が鉄則だと言われており、この3つの活動を地域でどうやって徹底してやっていくかが重要であるとされている。
県としてこの地域ぐるみの活動を支援する取組は何か行っているのか。
【野生イノシシ対策室長】
地域ぐるみでの活動を支援するため、被害防止対策推進費のうち、人材育成活動として鳥獣被害対策モデルケース育成事業を2022年度から開始している。この事業は、地域全体での鳥獣被害対策のための活動を強化することによって農業被害を防ぐことを目的に、地域の農業者などを対象とした現地研修会を開催するものである。
2022年度は、鳥獣被害が大きい豊田市大野瀬町梨野地区と新城市大字作手保永和田地区の2地区で実施をしており、梨野地区では研修会を6回開催し、延べ66人が参加、和田地区では研修会を5回開催し、延べ87人が参加した。
この事業によって、鳥獣被害対策の3本柱である、寄せないための生息環境の管理、近くに入らせないための侵入防止柵の設置、個体数を減らすための鳥獣の捕獲などの各対策や、それらの対策を地域ぐるみで徹底して取り組む重要性についての理解が進み、地域住民による周辺環境や侵入防止柵の点検、整備、シカやサルの効果的な捕獲対策の検討などの取組が始まっている。
この事業は、引き続き今年度も実施していることから、今年度の取組内容も含め、取組によって得られた成果は、今後、県のウェブページへ掲載するなど情報発信を行うとともに、農業総合試験場や各地域の農業改良普及課と連携し、こうした取組が必要な地域に横展開を図っていきたい。
【日比たけまさ委員】
最近、クマの話題が持ち切りである中、先週には私の住む春日井市内でもクマと見られる足跡を県職員が確認したとのことで、正直、驚きと同時に危惧している。
鳥獣被害の背景の一つは、高齢化による荒廃農地の増加により、野生鳥獣の生息域が拡大している。鳥獣被害は離農の動機にもなり、被害を防ぐ対策を継続的に進めてもらうことが集落の維持にもつながるため、先ほど触れた対策の3本柱を実践するために新しい技術の導入、そして、マンパワーが必要だと思うので、引き続き支援をお願いする。
<農林基盤局関係>
【日比たけまさ委員】
令和4年度決算に関する報告書263ページの森林環境譲与税活用事業費のうち、森林環境整備事業費について伺う。
森林の有する多面的な機能が発揮されるよう、森林の整備や木材利用を促進することは重要である。そして、これらの取組に必要となる森林に関する情報を関係者が取得し利用できる環境を整えることも重要な取組である。報告書には航空レーザ計測データを活用した森林情報の整備を行ったとの記載があるが、この森林クラウドシステムの開発について、システムの内容を伺う。
【林務課担当課長】
森林クラウドシステムは、森林に関する情報を電子データにて一元管理し、県、市町村、林業経営体がリアルタイムで共有し活用するためのものである。システムには、航空レーザ計測データの解析により取得した詳細な森林資源情報や地形情報が登載されている。これを活用することにより、杉やヒノキなど、一本一本の樹種の分布や樹高、太さ、面的な資源量の把握に加え、斜面の起伏や傾斜、林道や作業道、過去の崩壊跡地などを把握することができる。
また、これまで県で整理してきた森林簿や市町村が管理する林地台帳、過去の補助事業等の施業の実績も登載しており、森林所有者情報や過去の施業状況なども把握できる。
【日比たけまさ委員】
令和3年11月定例議会の代表質問で、この森林の持つ多面的機能の発揮に向け、所有者不明の森林に対する対策をどのように行っていくのかという質問で、その際、市町村が森林所有者に代わって経営管理を行う、いわゆる森林経営管理制度において、所有者不明森林の対策も行っていくとの答弁があった。
そこで、この森林経営管理制度の推進など、森林整備や林業振興において、今回開発した森林クラウドシステムにどのような効果が期待されるのか。
【林務課担当課長】
森林経営管理制度の推進において、市町村が森林所有者に代わって間伐などの森林管理を行うに当たり、まず最初に、手入れの行き届いていない森林を抽出した上で、森林所有者に対し経営管理の意向確認を行う必要がある。このシステムを活用することで、樹木の混み具合などから対象となる森林の抽出を容易に行うことができる。
また、森林整備や林業活動を進める上で重要となる土地の所有界の確認について、森林所有者の高齢化などにより年々困難になってくる。このシステムを用いることにより、樹種や樹齢の違い、尾根や谷などの地形情報を参考に境界の推定図を作成することで、現地に行くことなく隣接所有者同士による境界の確認が可能になる。こうした省力化等の取組により、効率的な森林経営管理や施業の集約化を図ることができる。
【日比たけまさ委員】
森林の持つこの公益的機能の発揮には、森林を適切に維持、管理することが必要である。市町村や林業経営体による効率的な森林整備の推進に向け、ぜひこの開発したシステムが活用されるようにしっかりと取り組んでもらうことを要望する。