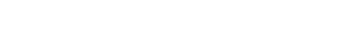令和5年 一般会計・特別会計決算特別委員会(2023.11.17)
<県民文化局関係>【日比たけまさ委員】
令和4年度決算に関する報告書30ページの人権推進事業費に関連して伺う。
2022年4月に愛知県人権尊重の社会づくり条例が施行されたが、施行に伴い新たに取り組んだこと、また、力を入れて取り組んだことがあれば伺う。
【人権推進課長】
条例施行に伴い、2022年4月から人権啓発及び教育の拠点であるあいち人権センター内に人権相談窓口を整備するとともに、一昨年度試行的に実施したインターネットモニタリング事業を本格的に実施した。また、新たに愛知県人権施策推進審議会を設置し、昨年度は主にヘイトスピーチ関連の取組について詳細を検討してもらった。さらに、性的指向及び性自認の多様性についての理解増進等の取組も充実させた。
【日比たけまさ委員】
今の答弁で出た、それぞれの取組について伺う。
初めに、人権相談窓口を整備したとのことであるが、窓口の体制や相談実績、評価、課題、今後の取組について伺う。
【人権推進課長】
人権相談窓口は、4人の人権相談員が様々な人権に関する悩みや問題について、電話や面談などにより受け付けて対応しており、昨年度の相談の実績は247件である。
相談区分別の実績として、障害者32件、プライバシー侵害20件、インターネット18件などとなっているが、いずれの区分にも属さないその他が116件と最も多くなっており、人権に関する悩みや問題を漠然と抱えている相談者にとっては、情報提供や助言、専門相談窓口や救済機関への案内が行われることで解決に向けた第一歩になっている。
課題としては、周知と他機関との連携であり、今後はより一層人権相談窓口の周知に努めるとともに、他機関との連携を図っていきたい。
【日比たけまさ委員】
次に、インターネットモニタリング事業を本格的に実施したとのことであるが、この取組の詳細や流れ、また、実績、評価、課題及び今後の取組について伺う。
【人権推進課長】
本県で行っているインターネットモニタリングは大きく分けて二つある。
一つは、業者に委託し、新型コロナウイルス感染症、部落差別、外国人、障害者の分野について、キーワード検索によって掲示板等の書き込みをモニタリングしている。
もう一つは、動画はキーワード検索では把握できないことから、職員が目視により行っており、主に部落差別関連の動画サイトをモニタリングしている。いずれも国の取扱い等に照らして、差別を助長する悪質で違法性が高いと考えられる投稿については、国の人権擁護機関である法務局に削除要請している。
昨年度の実績として、委託により差別を助長する書き込みの報告があったのは555件であり、内訳としては、コロナ70件、部落差別83件、外国人381件、障害者21件となっている。そのうち削除要請した件数は29件であり、実際に削除された件数は22件あることから、モニタリングは一定の効果があると考えている。
課題としては、直接的に悪質な書き込みを防止する方法がないことであるが、今後も継続してモニタリングしていくとともに、今年度からキーワード検索の対象分野に性的少数者を加えるなど、充実に努めている。
【日比たけまさ委員】
次に、新たに設置した愛知県人権施策推進審議会では主にヘイトスピーチ関連の取組の詳細を検討したとのことであるが、どのような検討や議論を行い、その結果はどうであったのか。また、今年度の審議会では何を主に議論しているのか。
【人権推進課長】
審議会での、条例に定められているヘイトスピーチの解消に向けた取組は二つあり、一つは県が設置する公の施設において、ヘイトスピーチが行われることを防止するための指針を定めること、もう一つは、公の場所でヘイトスピーチが行われたと認められるときは、その概要を公表することである。昨年度の審議会においては、この指針及び概要の公表の具体的な事務処理について検討を行った。
また、概要を公表する場合は申出により審議会の意見を聴いて判断することになっているが、昨年度は1件申出があり、審議の結果、ヘイトスピーチには該当しないとの答申をもらっている。
今年度は条例に基づき人権施策に関する基本的な計画を策定することとなっており、現在その内容について検討してもらうとともに、計画に盛り込む予定のファミリーシップ制度の内容についても主に議論をしてもらっている。
【日比たけまさ委員】
最後に、性的指向及び性自認の多様性についての理解増進等の取組を行ったとのことであるが、具体的にどのような取組を実施したのか。また、そうした取組に対する評価や課題、今後の取組について伺う。
【人権推進課長】
条例には性的指向及び性自認の多様性について、県民及び事業者の理解を深めるための取組を行うことと、県が事務事業を行うに当たり、その多様性に配慮する旨の二つが規定されている。
そこで、まず県庁内での理解を図るため、性の多様性に係る庁内連絡会議を設置し、申請書等における性別記載欄の見直しを行うとともに、性の多様性に関する職員ハンドブックを作成した。また、事業者の理解を深めるため、企業とLGBTと題した講演会をオンラインで開催し、それに併せて啓発資料も作成した。
評価であるが、性別記載欄の見直しでは合理的な理由のない申請書等の性別記載欄を60件廃止し、職員ハンドブックは職員以外からも参考にしたいとの問合せがあった。また、講演会では90人の参加があるなど、一定の評価ができると考えている。
課題としては、性的指向及び性自認の多様性についての理解がまだ不足していると考えており、今年度は引き続き庁内連絡会議を開催するとともに、職員ハンドブックの使い方の研修を行うなど理解を深めるための取組を行っていきたい。
また、LGBTの人々、特に若者は性的少数者としての生きづらさや困難さを保護者にも相談できない状況があると聞いており、今年度は若者向けの取組も行っている。
具体的には、当事者だけでなく全ての若者を対象とした若者向け啓発資料や、相談対応者及び指導者向けのガイドブックを作成している。こうした取組を進めることにより、性の多様性に関する理解増進を図る予定である。
【日比たけまさ委員】
近年、人権に関する課題の複雑化及び多様化が進む中で、県民の関心も高まっていると感じている。この条例の第1条には「あらゆる人権に関する課題の解消を図るとともに、全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目指す」と記載されており、引き続きこうした目的を達成するために施策が展開されることを要望する。
<環境局関係>
【日比たけまさ委員】
令和4年度決算に関する報告書51ページの環境基本計画推進費について伺う。
報告書にはあいちSDGs環境プラットフォームの構築を行ったと記載があるが、この事業に対する費用はどれだけであったのか。また、この事業の目的、内容及び結果の評価について伺う。
【環境政策課担当課長】
あいちSDGs環境プラットフォームについては、SDGs達成に向けた取組の拡大、向上、活性化を図ることを目的として、県内の企業、団体、大学、NPOなど様々な主体が実施しているSDGs達成に向けた環境面の取組を登録してもらいデータベースを構築し、それらの取組をほかの企業等に参考にしてもらうためのウェブサイト上のプラットフォームであり、費用は1,145万3,454円となっている。
具体的な内容であるが、登録者が取組事例を写真や動画を用いてウェブサイトに登録することで、広く自らの取組内容を発信することが可能となるだけでなく、そうした内容を基に登録者間でマッチング希望を発信することにより新たな連携先を探すことが可能となる。さらに、データベースを構築したことで、ウェブサイトの閲覧者は業種、取組分野などユーザー目線の検索機能により様々な団体の取組等の情報を容易に取得することができ、自らの行動、取組の参考にすることができる。
このプラットフォームは昨年9月末に開設し、約半年で目標の50団体を上回る57団体に登録してもらい、SDGsの環境面からの取組の促進に一定の効果があった。
【日比たけまさ委員】
多様な主体のSDGs達成に向けた環境面の取組をより一層促進していく観点でいえば、プラットフォームの登録者数をさらに増加して利用拡大を図っていく必要がある。
そこで、プラットフォーム利用拡大に向けた今年度の取組状況を伺う。
【環境政策課担当課長】
プラットフォームの登録者の増加に向けては、これまでSDGs AICHI EXPOなどの各種イベントでのチラシ配布、各種メールマガジンでの紹介など様々な機会を通じて登録を働きかけ、登録者を増やしてきた。しかしながら、SDGsは環境のみならず、経済、社会という側面があり、SDGs全般を所管する政策企画局においてこの三つの側面全ての取組を行う企業、団体等を登録する愛知県SDGs登録制度を2021年9月から運用しており、二つの制度が共存している状態になっていた。登録を希望する企業、団体等からは分かりにくいと意見があり、また、SDGs達成に向けては各側面での取組を進めることが必要であることなどを踏まえ、政策企画局と連携して両制度を発展的に統合することとした。
具体的には、環境プラットフォームをベースに、経済、社会面の取組を登録できるようにするなど改修を行い、本年10月2日から新たな登録制度、あいちSDGsパートナーズとして運用を開始した。また、新たな制度の運用開始に合わせ、モリゾーとキッコロをあいちSDGsアンバサダーに任命し、SDGsの取組促進のPRを進めている。
新しい登録制度やアンバサダーは政策企画局が運用していくが、環境局としても、環境面からのSDGsの取組の普及促進に向け、政策企画局と連携しながら取り組みたい。
【日比たけまさ委員】
県民、企業及び団体のSDGsに対する認識が高まる中で、利用する側にとって分かりやすいサイトにバージョンアップすることは大切だと思う。私もピンバッジをつけているが、モリゾー、キッコロという県民にとって親しみのある、また、SDGsの概念と親和性の高いキャラクターを用いて広報啓発するとのことである。ぜひ多くの企業、団体に登録してもらい、新たなプラットフォームがSDGsへの取組のデータベースとして、見える化やマッチング促進につながる当初の目的がしっかり推進されるよう要望する。
続いて、令和4年度決算に関する報告書74ページのPCB廃棄物適正処理推進事業費について伺う。
報告書には、会社の倒産等により処理義務者が存在しなくなった高濃度PCB廃棄物処理を4件、行政代執行したと記載されている。このPCB廃棄物の処理に関して、今までどのような取組を行ってきたのか。
【廃棄物監視指導室長】
一般にはPCB特別措置法と言われている、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、PCB廃棄物を保管する事業者には、毎年度その保管状況を知事に届け出ることが義務づけられ、国が定めた処分期限までにその処分が義務づけられている。
本県では、県内に存在するPCB廃棄物が期限内に処分されるよう、国が定めた未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起こし調査マニュアルなどに基づき、2013年度から2020年度にかけて繰り返し掘り起こし調査を約11万8,000社に対して実施し、変圧器、コンデンサなどを約1,600台新たに確認するとともに、その処分を指導した。当初の処分期限である2021年度には、処分期限後に高濃度PCBが発見されることのないよう、過去に変圧器、コンデンサなどを設置した事業者約2万3,000社に最終的な確認依頼と処分期限を周知する通知も行った。
本県では、こうした取組を通じ、これまで変圧器、コンデンサなど3万4,200台、安定器など1,275トンを処理してきた。2022年度も新たに判明した高濃度PCB廃棄物の保管事業者などに対し、処分を完了するよう事業者指導を行い、処分義務者が存在するものについては全て処分されている。
一方で、破産により処分義務者が存在しなくなった4件については、国の助言に従い、行政代執行による処分を行った。
【日比たけまさ委員】
高濃度PCB廃棄物の処分期限が2024年3月末に迫っているが、今後どのように取り組んでいくのか。
【廃棄物監視指導室長】
2023年10月末現在、本県では高濃度PCB廃棄物がいまだ処分されていない案件はないが、国の高濃度PCB廃棄物処理事業が本年度末、2024年3月末までに処分期限が延長されているため、発見があった場合は直ちに処分するよう、保管事業者に指導を行う。
また、処分期限を踏まえた国の通知により、保管事業者と処分業者との処分委託契約の期限が今年の12月末となっていることから、これを過ぎても保管事業者による処分が行われない場合や、保管事業者が不存在である場合が今後出てきた場合には、PCB特別措置法第13条に基づく代執行により処分を行う。
【日比たけまさ委員】
これまで県内に数多く存在していた高濃度PCB廃棄物に対して、設けられた期限での処理に向けて長期にわたって計画的に業務を執行し、さらに、計画的処理期限が過ぎた後も廃棄物ゼロに向け業務を愚直に遂行してもらった結果、愛知県管理分としては、現時点では廃棄物ゼロになっているとのことで、本当にありがたい。
今後、高濃度PCB廃棄物も低濃度PCB廃棄物の処理もあるため、関係機関、業界団体等と連携を図りながら、業務を適切に進めてもらいたい。