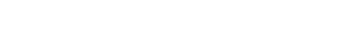令和6年 総務企画委員会(2024.6.27)
【日比たけまさ委員】
大きく2項目、一つ目は、職員の総労働時間削減に向けた取組、二つ目は、能登半島地震の復旧復興支援に従事する職員に向けた取組について質問する。
私は、本年度、5年ぶりに総務企画委員会の委員となった。5年前もちょうどあいち行革プランの策定のタイミングであり、本委員会において2018年度の時間外実績である年間148.7時間に触れながら職員の出退時間管理をシステム化してほしいという内容も含め、適正な労働時間管理の徹底を要望した。
あいち行革プラン2020後半期の取組を確認すると、時間外勤務時間数の数値目標が、2019年度実績である年162.3時間から毎年度減少させるとなっている。この目標自体があいち行革プラン策定時を上回る値となっているが、近年の時間外勤務の実績は、どのように推移しているか。増減要因も踏まえて伺う。
また、人事院規則で定める超過勤務の上限時間は、原則1か月あたり45時間かつ1年あたり360時間の範囲内となっているが、例外的に最大四つ、1か月あたり100時間未満、2から6か月平均で月80時間以下、1年で720時間まで、月45時間超過は年6か月までの範囲が認められている。
そこで、この最大値を超える職員は、直近で存在するのか。
また、以上を踏まえて、時間外勤務の削減に向けてどのような対応を図っているのか。
【監察室長】
知事部局等における職員1人当たりの時間外勤務の推移は、日比たけまさ委員が示したとおり、2019年度は162.3時間であり、その後、2020年度は162.4時間、2021年度は182.0時間、2022年度は185.8時間と増加が続いた。昨年度は、新型コロナウイルス関連業務が落ち着いたこともあり、174.3時間と減少に転じている。
あいち行革プランの目標値に比べて時間外勤務が増加した要因としては、2019年度末から約3年以上にわたる新型コロナウイルス関連業務や能登半島地震への対応など、全庁的な動員が必要となる不測の事態が発生したことや、数々の主要プロジェクトが実現に近づき、事務量が増えたことが大きな要因ではないか。
次に、長時間の時間外勤務を行った職員の状況である。
大規模災害への対応など上限が適用されない業務に従事した時間も含むが、2023年度は、知事部局では268人が該当している。内訳は、月100時間以上の者が139人、複数月の平均で80時間を超えた者が169人、年合計で720時間を超えた者が67人、月45時間を超える月数が6月を超えた者が135人となっている。これらの数字も前年度に比べて全て減少している。
最後に、時間外勤務を縮減するための取組であるが、全庁一斉定時退庁日の設定や幹部職員による消灯観察、時間外勤務縮減キャンペーンのほか、長時間勤務者がいる所属へのヒアリングや管理監督職員への研修など、マネジメントの強化や時間外勤務の削減に向けた意識啓発を図るために各種の取組を継続的・複合的に進めている。
【日比たけまさ委員】
2022年7月からは、職員の勤務時間管理にパソコンのログ記録が活用されるようになったと聞く。導入について、私は5年前からシステム化してほしいと言われており、大きな前進だと思っているが、ログ管理を活用する中でどのような影響が出ているのか。
【監察室長】
職員の勤務時間管理は、原則として上司が現認することで確認している。時間外勤務のように退庁時間の現認が難しい場合は、従事内容、従事時間の確認を踏まえた事前命令や事後確認を徹底するなどして適切な勤務管理を図っている。
こうした中、勤務時間を客観的に把握するために、2022年度にパソコンのログ記録を活用した勤務時間管理を導入したところであるが、勤務時間が明確に記録されるため、職員の中で時間外勤務や勤務時間に対する意識が従来よりも明らかに高まってきていると思う。意識することで具体的な行動の実践につながってくるため、引き続き職員に対する研修など意識啓発に努め、導入の目的である長時間勤務の是正や職員の健康確保につなげていきたいと思っている。
【日比たけまさ委員】
本県は、ワークライフバランスの充実と生産性向上による経済活性化を目指した休み方改革を提唱している。その中で年末年始の連続休暇取得推進など、新たな取組も始まった。そこで、職員の休み方改革の内容や結果はどのようになっているのか。
【監察室長】
職員の休み方改革について、昨年度の年末年始には、休暇取得率7割程度を目安に最大12連休となる連続休暇の取得促進に取り組み、期間中における平日3日間の平均休暇取得率は、53.6パーセントとなった。その後実施した職員アンケートの結果なども踏まえて、今年度も職員の連続休暇の取得促進に取り組んでいる。
まず、大型連休に合わせた連続休暇の取得促進では、昨年度の年末年始に行った取組をゴールデンウイークと盆にも拡大している。半数を目安に休暇取得を奨励しているが、先日のゴールデンウイークにおける平日3日間の平均の休暇取得率は32.5パーセントとなっている。さらに、時期分散型の連続休暇として、職員が希望する時期にマイ・ウィークを設定し、マイ・ウィークの7日間の中で土日・祝日と休暇をつなげて5日間以上の連続休暇を取得するあいちマイ・ウィーク・プランを実施している。あいちマイ・ウィーク・プランは、7月と11月を推進月間として設定しており、連続休暇取得の機運をさらに高めて取り組んでいる。
【日比たけまさ委員】
ただ今、時間外勤務や休暇等について聞いたが、その他の柔軟な働き方の取組としてテレワークや在宅勤務があるが、近年はどのように取り組んでいるのか。
【監察室長】
職員の柔軟な働き方を推進する取組として、2002年4月から時差勤務制度、それから2020年1月から在宅勤務制度を導入している。
近年の取組について、まず、時差勤務制度は、より利用しやすい制度となるよう、昨年4月から見直しを行った。具体的には、これまでは子の養育や家族の介護、長距離通勤などの指定事由を限っていたが、事由を問わず可能にしたことと、原則1か月単位であったものを一日単位で取れるようにしたことである。また、2週間前までに書面での申出が必要であったものを、前日までに口頭の申出で可能にしたことといった改正を行った。
次に、在宅勤務制度は、昨年度、在宅勤務時に時差勤務の実施を可能とし、7月、8月に在宅勤務集中取組週間を設定するなどの利用促進に取り組んでいる。また、今年度からは、対象者を一般職非常勤職員に拡大するとともに在宅勤務等手当を導入するなど、さらなる制度拡充を図っている。
引き続き、職員の多様で柔軟な働き方を実現できるように取り組んでいく。
【日比たけまさ委員】
総労働時間の抑制及び柔軟な働き方への取組としてフレックスタイム制度の導入、さらには週休3日も可能とする企業や自治体が増えている。これらの導入について、本県ではどのように考えているのか。
【監察室長】
フレックスタイム制だが、国では、昨年8月の人事院勧告を受けて、来年4月から全職員を対象に選択的週休3日を可能とするフレックスタイム制が導入されることとなっている。また、都道府県においても既に23の都府県が導入している。
フレックスタイム制は、ワークライフバランスの推進はもとより、職員の健康確保やモチベーションの向上、職場の魅力向上など様々な効果が期待をできると思っている。それが公務能率の向上や時間外勤務の縮減、優位な人材確保につながるのではないかと考えられる。
このような中、本県においても多様で柔軟な働き方をより一層推進するために、どのような方法がよいのか検討を進め、今後方向性を出していきたい。
【日比たけまさ委員】
5年前にも要望したが、生産性向上に向けて労働環境の改善、特に人事院の規制で定めている上限時間を超える職員を出さないことが必須だと思っている。本会議でも、知事から次期あいち行革プランの方向性として、時代に先駆けて仕事の進め方や働き方を見直し、職員、組織のアップグレードを行うとの発言があった。この観点からも、今後の検討に十分に反映されることを要望する。
次に、能登半島地震の復旧復興支援に従事する職員に向けた取組について質問する。
私は、2月10日から12日にかけて、石川県志賀町を中心にボランティア活動を行った。志賀町は本県の対口支援先となっているため、私は志賀町役場や避難所での炊き出し等を通じて、本県職員及び県内各市町村の職員が懸命に活動に当たっている姿を目の当たりにした。先ほど杉江繁樹委員から要望があったが、本委員会に付託された第106号議案が本会議において可決された際には、いち早くこの災害応急作業等手当が支給されることを望むとともに、各市町村においても同様の手当が支給されることを期待し、質問に入る。
初めに、災害応急作業等手当の県内の市町村の状況を伺う。
【市町村課担当課長】
災害応急作業等手当が含まれる市町村の特殊勤務手当の支給状況は、毎年、全国の地方公共団体に対して総務省が実施する地方公務員給与実態調査において、支給される手当の概要を調査している。昨年4月1日現在、一般職の職員が災害等において危険な業務に従事した場合に手当を支給することとなっている団体は、23団体となっている。
【日比たけまさ委員】
災害応急作業等手当に関して、本県では、県内市町村に対してどのような対応を行ったのか。
私は、同一の災害で派遣されたのであれば、できる限り一律で支給されることが望ましいと考えるが、県として今後どのような対応を行っていくのか。
【市町村課担当課長】
特殊勤務手当は、各市町村の実情に応じて、各団体において判断した上で条例及び規則により定めるものであるため、県から市町村に対して一律に支給を求めることは難しいと考えられる。
しかし、本年1月19日付けで総務省より災害応急作業等手当の運用について通知があり、例えば、避難所運営等の業務や罹災証明に係る家屋調査等についても支給対象作業に該当し得るなど具体的な業務を例示し、手当を適切に運用するよう求める内容であったため、本県では、この総務省通知に沿って適切に対応するよう県内各市町村等にお願いした。
今後の対応としては、通知に沿った対応がされるよう、改めて助言していきたい。
【日比たけまさ委員】
各自治体の労働条件に県として口を挟むことができないという原則はもちろん理解しており、復旧復興に向けて懸命に活動している職員が手当のことを気にしているとは思っていない。
しかし、作業によってできる限り格差が生じないよう、県として助言を行うことを要望する。
次に、現地では、避難所運営や罹災証明の発行といった緊急的にマンパワーが必要となる業務がある一方、インフラ整備をはじめ、中長期にわたり技術的・専門的知識を要する職員が求められることもある。こうした職員は、各自治体において限られた人数しかいないこともあり、苦慮するという声も聞く。この点について県としての認識を伺う。
【人事課担当課長】
近年、市町村を中心に各自治体において土木職などの技術職員が不足しており、確保が厳しい状況となっている。一方、大規模災害時には、被災自治体から技術職員の中長期派遣への要望が高くなっている。こうした状況を背景に、総務省では2020年度から復旧・復興支援技術職員派遣制度が創設された。
この制度は、都道府県等が技術職員をあらかじめ確保して、平時は技術職員不足の市町村支援を行うとともに、大規模災害時の中長期派遣要員を確保する仕組みとなっており、国が地方交付税措置により人件費を負担するものである。
総務省は、全国で1,000人程度の登録を目指すこととしており、昨年4月1日現在での登録者数は全国で277人となっているところ、本県では、2021年度から新たに定数措置を行い、現在、土木職10人、農業土木職6人、建築職2人、林学職2人の合計20人を登録しており、全国トップレベルの登録者数となっている。
【日比たけまさ委員】
県の活用状況はどのようになっているのか。
【人事課担当課長】
復旧・復興支援技術職員派遣制度を活用した被災地派遣は、昨年度から令和2年7月豪雨関係で熊本県芦北町へ1人、今年度から令和6年能登半島地震関係で石川県能登町へ4人の合計5人の職員を派遣している。今後もこの制度を活用して、平時には市町村支援業務を行いながら、大規模災害時に総務省から派遣要請があった場合には、迅速かつ適切に対応していきたい。
【日比たけまさ委員】
人材確保が厳しさを増す中、民間企業とは異なる採用方法も含め、公務員を希望する受験者が減少している話をよく聞く。特に技術職の人材確保は喫緊の課題であり、自治体によっては、奨学金制度の創設や先行試験の時期、内容の見直しなど、競争が激しくなってる話も聞く。次期あいち行革プランの策定に当たっては、この点についてもしっかりと検討するよう、要望する。