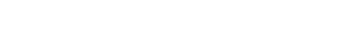令和6年 警察委員会(2024.3.15)
【日比たけまさ委員】
大規模地震発生時における警察活動について伺う。
地震発生は1月1日の16時10分、私は、妻方の親族と一緒に初詣に出かけていた。被災した人々を含め、多くの人は、1年で一番穏やかな時間を過ごしていたのではないか。そのような時間帯での発生にもかかわらず、警察は即座に対応し、現在も継続して対応している。
私は、2月10日から12日にかけ、石川県志賀町や内灘町を中心に炊き出しや倒壊した家屋の撤去作業といったボランティア活動を行った。現地では、各都道府県警察がパトロールや検問、そして安否不明者の捜索と推察される活動に従事している姿を目の当たりにした。もちろん県警察の部隊も見かけた。この場を借りて、懸命な活動に敬意を表する。
今回の能登半島地震では、県警察を含む全国警察の応援部隊が石川県警察に派遣されたものと承知している。このような大規模地震が発生した場合における警察活動について伺う。
【警備第二課長】
大規模災害発生時において被災地の公安委員会は、他の都道府県警察に対して援助の要求を行うことができることとされている。援助の要求を受けた都道府県警察は警察災害派遣隊を派遣し、救出救助、交通整理、検視、パトロールなどの警察活動に当たることとなっている。この警察災害派遣隊は、被災地警察の支援を受けることなく現場活動を行う即応部隊と、被災地警察の機能を補う目的で派遣される一般部隊とが編成されている。即応部隊である広域緊急援助隊は、救出救助、交通整理、検視を、広域警察航空隊は、上空からの情報収集、救出救助を、緊急災害警備隊は捜索や避難所などの警戒の警察活動を行うこととなっている。
一般部隊である特別警備部隊は捜索警戒を、特別交通部隊は交通整理を、特別自動車警ら部隊はパトロールを、特別生活安全部隊は避難所などでの相談対応を、特別機動捜査部隊は事件発生時における初動捜査を、身元確認支援部隊は身元確認に関する資料の収集などの警察活動を行うこととなっている。
【日比たけまさ委員】
県警察は、石川県警察と同じ中部管区に位置づけられることもあり、より多くの派遣がなされているのではないかと思う。そこで、能登半島地震に際して県警察から派遣された部隊について伺う。
【警備第二課長】
能登半島地震に際して、県警察では、警察災害派遣隊の即応部隊を直ちに招集し、1月1日午後6時頃に警察ヘリコプター1機5人、同日午後8時30分頃に救出救助に当たる部隊70人余りを派遣し、その後も継続的に交通整理、検視、パトロールなどを行う部隊を派遣している。
部隊派遣に必要な事務は支援対策室で行い、経理部、交通部、生活安全部、地域部、検視部が、即応部隊、一般部隊の派遣に必要な事務を担当し、警察庁及び地方機関である中部管区警察局と派遣事務に関する連絡調整を行っている。
県警察からは、3月8日現在、全国警察からの派遣総数約7万3,700人の約7.5パーセントに当たる延べ5,477人を派遣しており、その内訳は、即応部隊3,615人、一般部隊1,758人、その他防犯カメラ設置チームなど104人である。
今後も部隊派遣が見込まれているので、現在の支援体制を継続し、適切に対応していく。
【日比たけまさ委員】
30年以内に70パーセントから80パーセントと推定される南海トラフ地震の発生確率については、検討を行った政府の地震調査研究推進本部が、算出に使った特別な計算式のデメリットを科学的事実に反するおそれと資料に明記しながら、それを伏せたまま公表していたことが先週報道され、大きな話題となっている。しかしながら、本県としてできる限りの備えをしなければならない。このことについては、何ら変わることはないと思う。
そこで、愛知県で大規模地震が発生した場合の県警察の活動について伺う。
【警備第二課長】
県警察では、県内で震度6弱以上の地震を観測した場合、所属からの招集連絡を待つことなく、全署員が自主的に参集することとしているほか、職員の携帯電話に、けがの有無、参集に要する時間などの回答を求めるメールを自動配信するシステムを導入しており、迅速な体制確保に努めている。
体制を確保した上で、まずは人命を第一とした活動を最優先とする方針の下、110番通報、SNSといった情報源から、被害に関する情報を情報集約ツールである災害警備対策システムに集約し、整理、分析を行う。分析の結果、警察署で対応可能であれば警察署で編成された部隊で対応し、応援を要すると判断した場合は、警察本部から機動隊などの部隊を派遣して、救出救助、緊急交通路の確保、避難所対策、検視、被災地域のパトロールなどを行う。
また、防災関係機関が一体となった活動を行うことができるよう、本県警察が把握した被害情報については、県市区町村災害対策本部、自衛隊、消防機関などの関係機関と共有し、対策本部レベル、現場レベルで連携して対応していく。
【日比たけまさ委員】
全国の応援部隊が愛知県に派遣された場合の県警察の受入れ態勢について伺う。また、現在、愛知県が豊山町に整備を進めている基幹的広域防災拠点は、全国からの応援人員等を受け入れる後方支援活動を行う拠点としての役割を担っていると理解するが、県警察の活用方針について伺う。
【警備第二課長】
愛知県では、南海トラフ地震における愛知県広域受援計画を策定しており、南海トラフ地震などの大規模震災時における県外からの応援部隊の受援体制を定めている。この計画には、関係機関の応援部隊が当県に向かって移動する際の目標となる施設が指定されており、他の都道府県警察の応援部隊に関しては、名神高速道路の尾張一宮パーキングエリア、中央自動車道の内津峠パーキングエリアなどが指定されている。他の都道府県警察の応援部隊は、愛知県内の地理に関して不案内であるので、本県警察の連絡員が指定施設で出迎え、活動現場まで案内し、活動内容の調整を行うほか、これら応援部隊の宿舎を確保するため、愛知県ホテル旅館生活衛生同業組合の豊田市、美浜町、蒲郡市の各支部と警察の応援部隊の宿泊についての協定を締結し、協力してもらえることとなっている。
また、現在、愛知県が豊山町に整備を進めている基幹的広域防災拠点は、関係機関の応援部隊を支援する機能を有し、中部圏の基幹的な拠点として位置づけられているものと承知している。この拠点の供用開始に当たっては、他の都道府県警察の応援部隊が当県に向かって移動する際の目標施設とするとともに、ベースキャンプとしても活用することで、本県警察の受援体制がより強化されるものと考えている。
【日比たけまさ委員】
昨年12月22日に行われた警察委員会の県内調査にて、警察航空隊の活動について説明を受けた。また、今月3日に行った航空自衛隊小牧基地オープンベースで警察航空隊の展示飛行が行われ、私は、低空飛行からのホバリング、そして、警察犬を抱えた警察官が降下し、行方不明者の捜索に当たるという訓練の流れを見た。
さきの本会議での議案質疑では、警察ヘリコプターの平時の活動についての質問もあったが、大規模地震発生時における警察ヘリコプターの役割について伺う。
【警備第二課長】
大規模地震発生時において、警察ヘリコプターは、陸路ではアクセスが困難な孤立地域や離島に対し、上空からヘリコプターテレビシステムを用いた情報収集、救出救助、支援物資の搬送を主な任務としている。県警察では、平素から警察ヘリコプターの運航に関わるパイロット、整備士及び救助要員の操縦、整備、救助に関する能力向上を図っているほか、委員から紹介のあった警察ヘリコプターと警察犬が連携した救助訓練を行うなど、災害発生時に県民の期待に応え、迅速かつ安全に活動できるよう、万全を期している。
【日比たけまさ委員】
言うまでもないが、大規模災害は、その時々で状況が異なり、マニュアルどおりにいかないことが多々あると思う。そうした中での臨機応変に活動を展開できるか否か、これは初動活動では大変重要である。そのためにも、より多くの引き出しを持つことが求められる。
そこで、能登半島地震での活動を通じて得た教訓について伺う。
【警備第二課長】
このたびの派遣では、道路の損壊などにより、帯同した車両で必ずしも現場に到着することができない人が、現場で活動する関係機関の足かせとなった。本県警察も例外ではなく、1月1日に本県を出発した即応部隊は、石川県七尾市から先の道路が損壊しているとの情報を受け、同所に車両や大型の装備等を残したまま、持てるだけの資機材や食料、飲料水を携行して、陸上自衛隊のヘリコプターや海上保安庁の巡視船により活動エリアに入り、その後は徒歩での活動となったことから、各部隊員は精いっぱいの対応はしたものの、効率的な救助とはならなかった面もあった。
こうした経験を踏まえ、今後は、携行に適した資機材や部隊員が活動現場で手軽に補給できる携行食を充実させること、道路が損壊するなどしている状況下においても速やかに部隊を展開できるよう、小回りの利く小型車両を帯同すること、断水を想定し、テントつきの災害用簡易トイレ、手洗いなどに活用する雑用水といった、警察職員の健康管理に配慮した物品を整備すること、被災地での活動を終えた警察職員のストレスチェックと、その後のケアを行うことなどの対策を講じていく。
【日比たけまさ委員】
今回の対応を通じて、答弁でも様々な教訓が得られたとあったが、ぜひ、こうした情報の共有と、これまでの対応マニュアルについての再点検を、警察及び関係機関内でしっかりと図られたい。また、内容によっては、住民にもぜひ周知してほしい。
約3日前だが、県警察の公式ユーチューブチャンネルに、日本に住むインドネシア人の神父が体験した東日本大震災及び被災地支援についての動画がインドネシア語でアップされていた。外国人向け防災動画シリーズとの説明があったが、とても大切な取組だと思う。引き続き、ぜひ県民向けに様々な情報発信や呼びかけもお願いする。