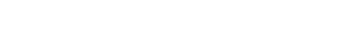令和5年 一般会計・特別会計決算特別委員会(2023.11.6)
<建築局関係>【日比たけまさ委員】
県営住宅について、三つの視点から伺う。
まず、決算に関する報告書313ページの長寿命化改善費について伺う。
社会情勢の変化により原油価格や資材価格の上昇が続いており、昨年12月には、政府の緊急経済対策として、物価高騰、賃上げへの取組が行われている。一方、県営住宅の長寿命化改善工事は、老朽化した住宅の機能を維持・更新するため、大変重要な事業である。
そこで、建設資材、人件費の高騰による長寿命化改善事業への影響はどのような状況であるのか伺う。
【公営住宅課担当課長】
長寿命化改善工事では、住宅を耐用年限まで安全に使用するため、屋上防水や外壁の補修、配管設備の更新などを行っている。近年、長寿命化改善工事においても資材価格や人件費が上がっており、工事の発注時にはこれらの影響を反映した最新の単価を採用するなど、適切に予定価格に反映して発注している。
また、工事期間中の資材価格や人件費の上昇については、公共工事標準請負契約約款に定めた条項等に基づき請負金額の変更を行い、工事に影響が出ないよう対応している。なお、昨年度は1件、本年度も1件の増額の変更契約を行っている。
今後も、建設資材等の価格変動について注視し、適切に対応する。
【日比たけまさ委員】
今後、カーボンニュートラルの推進、生産性の向上や建設業の働き方改革など取り組むべき課題が多く、コストの上昇が続くと見込まれる。その一方で、県営住宅は、住宅に困窮する人々のセーフティネットとして重要であり、住み続けるために長寿命化改善は着実に進める必要がある。
そこで、今後も事業費の上昇が予想される中で、この県営住宅の長寿命化改善事業を進めていくためにどのように対応していくのか伺う。
【公営住宅課担当課長】
2020年3月に策定した愛知県営住宅長寿命化計画では、計画期間の10年間で約4,000戸の長寿命化改善事業を行うことを目標としており、昨年度までの3年間で、1,056戸の長寿命化改善工事を実施している。
今後も、建設資材や人件費などの事業費の上昇を踏まえ、必要な予算の確保に努めるとともに、採用する工法の検討によるコストの縮減などに取り組み、着実に長寿命化改善事業を進めていく。
【日比たけまさ委員】
次に、滞納家賃の回収について伺う。
決算に関する付属書440ページの県営住宅管理事業特別会計第1款第1項第1目使用料について伺う。
県営住宅は、住宅に困窮する低額所得者のための住宅である、入居者の中には、一定の所得があるにもかかわらず家賃を滞納する人もおり、住宅使用料等で多額の収入未済が生じている。
これに対し、県では家賃滞納者に対して、住宅の明渡し等の訴えの提起や退去者の滞納家賃を外部委託により回収している。
そこで、長期悪質滞納者に対して行っている住宅の明渡し等の訴えの提起について、令和4年度の実績と効果について伺う。
【県営住宅管理室担当課長】
家賃を納付することのできない特段の事情がないにもかかわらず、再三の納付指導を行っても滞納家賃等の支払いに応じない長期悪質滞納者に対する、令和4年度の県営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴えの提起は、67人に対して行い、家賃等の滞納総額は2,549万932円である。訴えた67人中、和解者及び和解を予定している者が3人おり、これらの者を除く64人のうち55人は、既に自主的な退去または強制執行により、住宅の明渡しが完了している。残る9人についても、住宅の明渡しの強制執行を裁判所に申し立てており、現在、明渡しに向けて手続中である。訴訟の結果、和解による納付や敷金の充当によって、令和4年度の訴えに係る滞納家賃等については、令和5年10月1日時点で、440万7,750円を回収している。
また、金銭的な効果に加え、住宅の明渡しによって新たな入居者の募集を行い、県営住宅への入居を希望する人に対して住宅を提供できるようになった。
【日比たけまさ委員】
和解した人以外は、住宅の明渡しの手続を進めているとのことである。
また、裁判に限らず、退去後の滞納家賃の回収については外部に委託しているとのことであるが、この実績や効果はどのようになっているのか。
【県営住宅管理室担当課長】
県営住宅を退去した人の滞納家賃等の回収は、滞納者が転居しているため住所地の特定などが必要であり、県営住宅に入居中である滞納者に比べ、滞納家賃等の回収が難しい。このため、平成22年度から、退去した人の滞納家賃等の回収について、弁護士事務所への業務委託を開始した。委託先の決定に当たっては、公募で企画提案をもらうプロポーザル方式により、最も評価の高い者と契約している。
また、継続的に回収業務に当たる必要性があるため、契約期間を3年として、現在の契約は、令和4年10月から令和7年9月までとなっている。令和4年度における退去者の滞納家賃回収業務の実績は1,296万2,706円であった。
委託を開始した平成22年度から令和4年度までに、1億5,024万5,233円の滞納家賃等を回収しており、外部委託について一定の成果があったと考える。なお、弁護士事務所に支払う委託料は、回収額に応じた成功報酬制としており、現在の報酬率は20.8パーセントで、令和4年度の報酬額は269万6,236円である。
今後も、委託先である弁護士事務所との連携を図り、引き続き退去者の滞納家賃等の回収を進める。
【日比たけまさ委員】
最後に、県営住宅駐車場の有効活用について伺う。
決算に関する付属書440ページの県営住宅管理事業特別会計第3款第1項第1目財産貸付収入の土地貸付収入について伺う。
県営住宅では、住宅の建替時などに駐車場の整備を進めている一方、車の所有に対する考え方の変化や入居者の高齢化等により、車を所有しない人が増えている。その結果、県営住宅の駐車場の契約率は7割を切っており、駐車場に空き区画が目立つ住宅もある。
そこで、県では、こうした駐車場の空き区画を貸し付け、コインパーキングを誘致しているが、駐車場の空き区画の有効活用の実績はどのようになっているのか伺う。
【県営住宅管理室担当課長】
県営住宅駐車場の空き区画の有効活用として、平成27年度から民間事業者に対して駐車場の空き区画の貸付けを開始した。これまでに、瑞穂区の中山住宅、中川区の万場東住宅及び刈谷市の重原住宅で、コインパーキングの設置を希望する事業者に駐車場の空き区画を貸付け、また、瀬戸市の萩山台住宅では、学校法人に職員等の駐車場として貸付けを行っている。
この結果、令和4年度の駐車場の空き区画の貸付けによる土地貸付収入は、4住宅を合わせて302万2,920円である。なお、万場東住宅、重原住宅については、昨年11月からの貸付けのため、5か月分の賃貸料となっている。
【日比たけまさ委員】
それでは、今後の駐車場の空き区画の有効活用はどのように考えているのか。
【県営住宅管理室担当課長】
県営住宅駐車場の空き区画を活用したコインパーキングは、県営住宅への来訪者はもとより、県営住宅の周辺住民の利便性向上に寄与するとともに、路上違法駐車対策にも有効であると考えているため、引き続き、空き区画の有効活用としてのコインパーキング誘致を進めるため、コインパーキングに適した条件など事業者の意見を聴き、入居者の理解が得られた住宅でのコインパーキングの導入を図りたい。
【日比たけまさ委員】
平成30年度の県政世論調査によると、県営住宅のイメージについてという問いに、住宅に困窮する人のための住宅として役に立っていると答えた人の割合が44.0パーセントと最も高く、また、県営住宅の果たすべき役割についてという問いでは、母子世帯、老人世帯、障害者世帯など住宅の確保に特に配慮を要する人向けに低家賃で安定的に住宅を提供する役割と答えた人の割合が69.8パーセントと最も高いとの結果が出ており、多くの県民が公営住宅法に基づいて、住民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とした県営住宅の必要性について理解していると考える。
今回、三つの視点で質問したが、今後も、継続的に適正な管理が実施されることを要望する。
<教育委員会関係>
【日比たけまさ委員】
決算に関する報告書333ページの道徳教育推進事業費について伺う。
この事業は、人間関係をつくる力やコミュニケーション能力を養い、社会で自立して活躍できる人材を育成するため、道徳教育の実践や様々な体験活動、地域貢献活動を行っているとのことである。大変重要な取組であるため、この事業が実施された経緯と事業の推移、成果について伺う。
【高等学校教育課担当課長】
道徳教育推進事業は、地域貢献活動を通して生徒の豊かな情操や道徳心を育むことを目的として、2014年度から実施している。毎年、県立高校と特別支援学校の中から10校を指定し、地域の清掃や、高齢者や幼児、障害のある人々を対象としたボランティア活動、近隣小中学校との交流、小学生対象のモノづくり講座やプログラミング講座など、それぞれの学校の実情に合わせた地域貢献活動を行っている。
2022年度までの9年間で、県立学校178校中53校を指定して、事業を実施してきた。昨年度の実践指定校からは、地域貢献活動を通して、相手を尊重する態度や人間関係をつくる力、コミュニケーション能力を高めることができたという成果が報告されている。こうした実践指定校での取組や成果は、報告書にまとめて周知し、広くほかの学校にも還元している。
なお、令和5年度は、これまでの成果を踏まえて、実践指定校を10校から12校に増やしている。
【日比たけまさ委員】
実践指定校を今年度は12校に増やすとのことである。
とてもありがたい話ではあるが、年間の指定校が限られており、この取組を行った学校は翌年度も事業を展開したいと考え、実施できなかった学校は、翌年度にぜひ行いたいという希望があると思う。
そこで、実践指定校の選定はどのように行われているのか、また、選定されなかった学校へは、どのようにフォローしているのか伺う。
【高等学校教育課担当課長】
実践指定校については、指定を希望する学校から提出された企画書の内容を審査し、10校を選定した。
なお、本事業は、基本的に単年度で実施しているが、生徒の情操を育むことなどを目的とする事業のため、学校の状況によっては、同一校が複数年度にわたって実践指定校となる場合もある。希望しながら指定されなかった学校に対しては、過去の実践指定校の取組や成果を取りまとめた報告書を参考にして、翌年度に実施する地域の施設や団体と連携した企画を検討するよう助言するなど、翌年度のエントリーと指定につながるよう配慮している。
【日比たけまさ委員】
この事業費で活動を展開した校長に話を聞くと、学校外で取組を展開するために、まずは計画、そして実行、うまくできた点や改善点を肌で感じながら次につなげるPDCAサイクルを生徒たち自らが回すことで成長を感じ取ることができ、大変有意義な取組とのことである。特に、コロナ禍で外とのつながりが希薄になってしまったため、今後は積極的に展開していきたいとの話も聞いている。
また、この事業費が充てられたわけではないが、今夏に開催された春日井サイエンスフェスタには、市内にある県立高校が多数ブースを出展しており、私の小学生と幼稚園児の子供も、高校生から楽しい実験やプログラミングなどを教わり、とても喜んでいた。
現在、県立高等学校再編将来構想を検討して進めてもらっているが、県立高校の一層の魅力化、特色化、再編の五つのポイントが記載されているが、まさにこうした取組の推進が鍵を握ると思っているため、こうした事業は、より一層力を入れてもらいたい。
次に、決算に関する報告書359ページの家庭教育支援基盤形成事業費について伺う。
この事業費は、保護者等を対象に、訪問や電話等により家庭教育に関する相談や支援を行っている。近年、不登校児童生徒が増加する中で、とても大切な取組である。
そこで、家庭教育相談の実施状況として、相談件数140件、延べ相談回数5,234回と記載してあるが、具体的な事業内容や実施体制はどのようになっているのか伺う。
【あいちの学び推進課担当課長】
家庭教育相談は、退職した小中学校教員を家庭教育コーディネーターという相談員として、県内六つの教育事務所・支所に16人、あいちの学び推進課に1人配置し、不登校など家庭教育上の問題を抱える保護者からの電話やメールによる相談のほか、直接家庭を訪問して相談、助言を行っている。
また、教員、カウンセラーへの就職を目指す大学生が、ホームフレンドというボランティアとして30人登録し、児童生徒の話し相手や遊び相手の希望があった家庭を家庭教育コーディネーターと一緒に訪問して、相談活動を行っている。
なお、昨年度の相談件数140件のうち、不登校に関する相談が133件と大半を占めている。
【日比たけまさ委員】
市町村でも、同じような家庭教育相談事業を実施していると思うが、県としてどのような役割をしているのか。
【あいちの学び推進課担当課長】
家庭教育相談事業は、まずは、市町村で対応してもらうことを基本としている。しかし、市町村によっては十分な相談や支援が行えないケースもあるため、県が補完する形で相談活動を行っている。
【日比たけまさ委員】
家庭教育相談事業を実施したことにより、どのような成果があったのか。
【あいちの学び推進課担当課長】
2022年度に相談があった140件の中で、不登校に関する相談133件については、9割近くの116件が、登校できるようになる、校外の施設へ通えるようになる、外出できるようになるなど、相談開始時よりも状況が好転し、成果があった。
【日比たけまさ委員】
児童生徒の不登校数の増加に伴い、家庭教育コーディネーターとホームフレンドによる相談回数の増加が予想されるが、それに対してどのような対応をしているのか。
【あいちの学び推進課担当課長】
家庭教育コーディネーターによる相談回数は、児童生徒の不登校数の増加に伴い、2019年度の3,532回から、2022年度には5,234回になるなど、増加している。
コロナ禍により、家庭訪問による相談回数は減少したものの、電話、メールなどの相談回数は増えている。
2022年度には、家庭教育コーディネーターに対して継続的な相談や支援ができるよう、1人1台の相談用スマートフォンを配備し、電話以外にもメールやLINEのビデオ通話により相談できる環境を整え、相談者が気軽に相談できるようにしている。
また、保護者から、ホームフレンドの家庭訪問に対する要望が増えたことを受けて、2021年度には、ホームフレンドを8人増員して30人にした。ホームフレンドの家庭訪問回数は、2019年度の573回から、2022年度には860回になり、保護者の要望に応えることができた。
【日比たけまさ委員】
本県の不登校児童生徒数は、小学校では、令和元年度が3,710人であったものが、令和4年度には7,408人、中学校では、令和元年度が8,441人であったものが、令和4年度には1万3,367人と年々増加している。この対策としては、多方面からの方策が必要である。
その一つとして、本事業は有効に相談に応じてもらえる体制が必要だと思うため、ぜひ、十分な対応を取れるよう要望する。
<スポーツ局関係>
【日比たけまさ委員】
決算に関する報告書375ページの障害者スポーツ振興費について伺う。
私は、令和3年11月定例議会で行った代表質問の中で、障害者スポーツに係る項目を取り上げ、その際、障害者スポーツの普及拡大に向けた取組を進めていくという答弁をもらった。
そこで、障害者スポーツを推進するために令和4年度はどのような取組を行ったのか、特に、新たに実施した取組があれば、それはどのような内容、実績、成果があったのか伺う。
【競技・施設課担当課長】
令和4年度には、これまで行ってきた種目別スポーツ大会や愛知県障害者スポーツ大会、障害者スポーツの体験会、あいち障害者スポーツ連絡協議会の開催のほかに、機会創出、人材育成、交流促進の観点から、次の三つの新たな取組を実施した。
初めに、地域や医療機関での障害者スポーツ体験機会の創出のため、ボッチャやフライングディスクの用具を貸し出す事業を実施し、総合型地域スポーツクラブ3施設、リハビリテーション施設2施設、特別支援学校4校で活用してもらった。
次に、障害者スポーツを支える人材育成のため、三つのセミナーを開催した。ボランティアを育成するあいちパラスポーツサポーター育成セミナーに103人、障害者スポーツ指導員資格認定校の学生に資格取得を促す若手指導者育成セミナーに17人、活動休止中の指導員に活動再開を促す指導者リ・スタート支援セミナーに30人が参加した。
最後に、障害のあるなしにかかわらず、誰もがスポーツを通じて交流を深められるあいちパラスポPARKを開催した。県内の企業や大学と協力し、パラリンピアンのトークショー、ブースや福祉車両の出展などを行い、522人が参加した。
これらの新規事業は参加者からの評価も高く、令和5年度も引き続き実施している。
【日比たけまさ委員】
愛知県及び名古屋市は、10月3日にアジアパラリンピック委員会などと開催都市契約を締結し、いよいよ正式に、2026年10月に愛知・名古屋でアジアパラ競技大会が開催されることが決まった。大村秀章知事は会見で、大会の開催は多様性を尊重し、共生社会の実現に貢献する重要な社会的意義がある。しっかりと準備を進め、大会の成功に向け全力を尽くすと話している。
そこで、今後の障害者スポーツの取組をどのように進めていくのか。
【競技・施設課担当課長】
アジアパラ競技大会に向けて、障害者スポーツを理解し、応援するあいちパラスポーツサポーターの取組を推進し、学生も含めた幅広い年齢層を支える人材として育成していく。そして、認定したサポーターに対して、スポーツ大会や体験型イベント、あいちパラスポPARKなどでの継続した活動を促すことで、2026年のアジアパラ競技大会において、ボランティアリーダーの役割を担うことができるよう支援していく。
このほか、パラアスリートの強化育成を図るため、国際大会を目指すパラアスリートに対して、合宿、大会への参加費等に1人50万円まで補助するオリンピック・アジア競技大会等選手強化事業を実施している。
今後も、障害者スポーツの普及促進に努めるとともに、支える人材の育成や本県ゆかりのパラアスリートの強化などにより、2026年のアジアパラ競技大会の盛り上げにつなげ、障害者スポーツのさらなる裾野拡大を図っていきたい。
【日比たけまさ委員】
私は、アジア・アジアパラ競技大会推進特別委員会に所属しており、8月に行われた委員会では、公益財団法人日本パラスポーツ協会、安岡由恵氏に話を聞く中、アジアパラ競技大会の開催の意義として、ただ単にパラスポーツへの理解で終わらせず、パラスポーツを通じた共生社会への理解につなげることがとても大切であると学んだ。
障害者スポーツの普及拡大は、その一翼を担うと思うため、さらに力を入れてもらいたい。