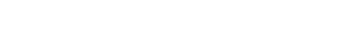令和5年 一般会計・特別会計決算特別委員会(2023.11.21)
<防災安全局関係>【日比たけまさ委員】
決算に関する報告書18ページの産学官連携地域強靱化推進事業費について、報告書には、あいち・なごや強靱化共創センターを運営し、産業の早期復旧対策など地域強靱化に係る調査研究や人材育成等を行ったと記載されている。
そこで、強靱化共創センターとはどのような組織で、どのように運営されているのか。
【防災危機管理課担当課長】
強靱化共創センターの組織運営について、あいち・なごや強靱化共創センターは、大規模災害発生時において、愛知・名古屋を中核とした中部圏の社会経済活動が維持されるための研究開発や事業を推進するために、2017年6月に名古屋大学、名古屋市と共同で設置した組織である。
事務局は名古屋大学の減災館の中にあり、事業計画や予算など組織の運営については、名古屋大学のみでなく、県、名古屋市、国土交通省中部地方整備局といった行政機関のほか、中部経済連合会、名古屋商工会議所といった産業界も参画する運営協議会で決定することとしており、産業界の協力を得ながら運営しているのが本センターの特徴となっている。
センター長には、開設以来、福和伸夫名古屋大学名誉教授が就任しており、副センター長は県の防災危機管理課長となっている。運営スタッフは、県職員、名古屋市職員、名古屋大学の教職員で構成している。
センターの運営経費については、2022年度の決算額で5,683万2,000円となっており、このうち愛知県からの負担金は1,098万3,000円となっている。このほかの主な収入額は、名古屋市からの負担金362万円、名古屋大学の運営費1,000万円、企業からの寄附金等885万円となっている。これ以外にも、受託事業収入や受講料等の収入がある。
【日比たけまさ委員】
あいち・なごや強靱化共創センターの事務局がある減災館では、防災に触れて学ぶことができる教材があり、様々な講習会やセミナーが開かれたと聞いている。そうした施設を生かして人材の育成を図り、地域の防災力を向上させる取組は大変重要である。
そこで、具体的にどのような人材育成を行い、どのような実績があるのか。
【防災危機管理課担当課長】
あいち・なごや強靱化共創センターにおける人材育成として、中小企業のBCP策定等の産業界の防災力を強化する産業支援、地域で活躍する防災人材を育成する県民支援、市町村の防災担当職員の専門知識を付与するための行政支援、あいち防災協働社会推進協議会と連携し、防災に関する幅広い知識を習得するための防災・減災カレッジの四つの事業を実施している。
それぞれの主な実績について、産業支援では、愛知県商工会連合会主催の経営指導員等応用研修会に講師を派遣したほか、BCP策定中あるいは策定済みの中小企業を対象として講習会を実施し、24人が受講した。
県民支援では、要配慮者利用施設向けの防災講習会及びBCP策定講習会を実施し、209人が受講した。また、防災人材の交流の場として、防災人材交流シンポジウム、つなぎ舎をあいち健康の森公園プラザホールで開催し、約220人が参加した。
行政支援では、市町村防災担当職員等を対象として、行政の人材育成研修を実施した。具体的には、災害救助法、被災者生活再建支援法事務研修、住家の被害認定研修、災害対策本部運用研修等の10種の研修を実施し、延べ722人が受講した。
防災・減災カレッジでは、防災基礎研修のほか、市民防災コースと五つのコース及び四つの選択講座等を実施し、延べ2,003人が受講した。また、当カレッジは防災士養成講座としての認証を受けていることから、受講生のうち139人が防災士として登録された。
【日比たけまさ委員】
昨年度、安全・安心対策特別委員会の県外調査で宮城県立多賀城高等学校を視察した際、この防災系の専門学科として全国でも2例しかない災害科学科の教育概要について、また塩竈市にある津波防災センターでは、東日本大震災発災直後1週間を中心とした市民生活と行政の対応について質問した。
一方、本県では、幸いなことに、近年、全県域に及ぶ大災害を経験していないこともあり、決して県民の防災意識が高い地域とはいえない。意識は地域によって差があると思うので、ぜひ他県の事例も参考にしながら、引き続き防災教育に力を入れてもらいたい。
続いて、令和4年度決算に関する報告書23ページの救急高度化対策費について、救急救命士を52人養成したと記載されている。
そこで、本県においては現在何人の救急救命士が市町村の消防本部に在籍しているのか。
【消防保安課担当課長】
県内の消防本部の救急隊の数は、令和4年4月1日現在で247隊となっており、各救急隊には、少なくとも一人以上の救急救命士の配置が望ましいことや、救急隊は24時間の交代勤務であり、交代要員のことも考慮して、各市町村で必要人数を配置している。
県内の消防本部において救急救命士の資格を有する者の数は、令和4年4月1日現在で1,632人が在籍しており、そのうち1,410人が救急隊として運用している。
【日比たけまさ委員】
具体的に、新規養成はどのように行っているのか。
【消防保安課担当課長】
救急救命士の国家資格を取得するため、研修所に入校し養成している。令和4年の実績の52人の内訳は、一般財団法人救急振興財団の東京研修所で34人、名古屋市消防局の研修所で14人、大阪市消防局の研修所で4人の養成を行った。研修に係る費用は、救急振興財団の研修施設は全国からの負担金で運用されており、救急隊の数や人口等を案分して、本県は2,120万円を支出している。
また、名古屋市の研修所には、市との協定に基づいて、教育に必要な備品を購入する形で県が負担しており、令和4年度は約247万円の備品を購入した。
【日比たけまさ委員】
一方で、報告書には1,173人の救急救命士に対し再教育を実施したとの記載がある。この再教育とはどのようなことを実施しているのか。
【消防保安課担当課長】
消防本部で運用されている救急救命士は、処置の質の確保及び維持向上のため、国の通知に基づいて、2年間で128時間の再教育を受けることとされている。1年当たり64時間の再教育のうち、本県が16時間を担って教育実習をしており、残りの48時間は消防本部ごとでの教育や病院実習が行われている。
本県における再教育は、毎年度、外傷や小児といった個別テーマを3項目ほど選定して、講義講習を8時間、実技講習を8時間実施している。講習講義では、テーマに沿ったDVD教材を作成して、eラーニング形式による教育を行い、課題シートを提出している。DVD教材であるため、過去のテーマも含めて、各消防本部で再活用できるようにしている。実技講習は、集合型教育として県が開催し、DVD教材で学んだ内容に基づいて実技訓練やグループワークを実施している。
なお、令和4年度は、県内4地区に分けて会場を設け、外傷、骨盤固定、循環器疾患などをテーマとして、実践的な技術の維持向上を図っている。
【日比たけまさ委員】
救急車による出動件数及び搬送人員は、近年コロナの影響もあり多少減少する時期もあったものの、基本的には増加傾向にあるため、救急救命士の必要性は年々高まっている。また、救急救命士に求められる知識や技能も年々高度化及び多様化している。
引き続き、消防本部が必要とする救急救命士の養成に適切に対応してもらうとともに、消防本部が行う再教育が効果的なものとなるように、より充実した教育資料作成や資機材の提供、また派遣病院との連携強化の部分で、県としてさらなる支援をお願いする。
<総務局関係>
【日比たけまさ委員】
令和4年度決算に関する報告書11ページのテレワーク環境整備費について、報告書には、職員の多様な働き方の実現や新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としての在宅勤務を支援するために配備したテレワーク専用端末1,100台の利用環境の整備を行ったと記載されている。
そこで、この事業内容はどのようなものか伺う。
【情報政策課担当課長】
テレワーク環境整備費は、令和元年度において、職員の柔軟な働き方の推進などを図るために試行導入したテレワーク専用端末100台と、令和2年度において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の一環として、職員の在宅勤務をより効率的に実施し促進するために追加導入した1,000台、合わせて1,100台を運用するための経費である。
導入したテレワーク専用端末は、いずれも5年間のリース契約としており、決算額3億8,818万3,224円は、令和4年度1年間の端末や管理サーバのリース料のほか、通信回線の使用や保守・運用などに係る費用の合計となっている。
【日比たけまさ委員】
このテレワーク専用端末は、主に職員の在宅勤務をより効率的に実施するために導入したとのことだが、専用端末というのはどのようなもので、導入した1,100台の配備状況はどのようになっているのか。
【情報政策課担当課長】
導入したテレワーク専用端末は、自宅や出張先においても庁内ネットワークに接続し、業務システムや公用メールを使用できるなど、庁内とほぼ同様の業務を行えるものである。仕様は、持ち運び可能な13.3インチのタブレット型パソコンで、通信は、インターネットから独立した専用回線を利用した上で、通信内容を暗号化するなどの強固なセキュリティ対策を講じている。
端末の配備に当たっては、全庁で広く利用できるよう、原則として本庁の各課室のグループごとに1台、地方機関では各課室に1台となるよう配備している。
【日比たけまさ委員】
今の答弁で、全庁で広く利用できるように、本庁及び地方機関の各課室に配備したことが確認できた。
このテレワーク専用端末の令和4年度の利用実績及び導入の効果を伺う。
【情報政策課担当課長】
テレワーク専用端末の令和4年度の利用実績は、全利用台数が延べ3万8,067台で、開庁日1日当たり、平均157台が使用されている。また、1日に最も多く利用された台数は435台であった。昨年度の職員へのアンケートによると、各種業務システムの利用をはじめ、メールやチャットを利用してコミュニケーションを取りながらの資料作成など、多くの業務に利用されている。
また、職員からは、職場にいるのと近い業務を行うことができたとの意見があり、職員の多様な働き方の実現に効果があったと考えている。
【日比たけまさ委員】
テレワークのメリットとしては、ペーパーレス化、デジタル化を促進、ワーク・ライフ・バランスが保ちやすい、人材確保につながる、事業継続性の確保など、かなり広く認識されており、現在ではハイブリッドワークが広がっている。県庁としても、新たな働き方として引き続き積極的に活用してもらうよう要望する。
続いて、令和4年度決算に関する報告書12ページの県有施設長寿命化推進事業費について伺う。
報告書には、愛知県公共施設総合管理計画に基づき、庁舎等の長寿命化改修等を支援するため、各施設への巡回点検を実施したと記載されている。
巡回点検を実施する目的や実施内容はどのようなものなのか。
【財産管理課担当課長】
巡回点検は、庁舎等の長寿命化対策を推進するに当たり、各施設における施設の健全性の確保や必要な長寿命化対策の取組を進めていく中で、施設管理者に対する技術的な支援を行い、施設管理者の専門知識、技術の向上を図るため、財産管理課職員が各施設を巡回して点検を行うもので、愛知県公共施設等総合管理計画が開始された2015年度から実施している。
昨年度は、長寿命化改修工事を実施予定の施設や工事を完了した施設を対象として、計40施設の巡回点検を実施しており、実施内容としては、長寿命化改修のための基本設計や実施設計の段階で、設計に盛り込むべき内容について、長寿命化改修基本調査に沿って適切に実施がされるよう確認指導を行うほか、長寿命化改修工事完了後において、今後の適切な予防保全のための維持管理方法について施設管理者に指導、助言を行ったところである。
【日比たけまさ委員】
巡回点検のほかに、施設管理者に対する支援は何か行っているのか。
【財産管理課担当課長】
施設管理者が長寿命化対策を適切に行うためには、施設の点検、診断結果や対策履歴等の情報を適切に管理、蓄積し、次の点検、診断に活用するメンテナンスサイクルを構築することにより、適切な時期に必要な対策を行うことが重要である。そのためには、施設の状態を正確に把握、管理する施設保全台帳の適切な整備が必要不可欠であることから、巡回点検に加えて、施設管理者向け技術研修会を開催し、施設管理者に対して施設保全台帳の適切な作成手法等について周知を図るなどにより、各施設が行う長寿命化対策を支援している。
【日比たけまさ委員】
2015年3月に策定された愛知県公共施設等総合管理計画の中で、膨大なストックを抱える県有施設の維持、更新に対して、事後保全から予防保全に切り替えて長寿命化を図ると位置づけ、取組が進められている。
その一方で、社会情勢の変化によって資材価格や人件費の上昇が続いており、この先も、カーボンニュートラルの推進や生産性の向上、建設業の働き方改革などの課題に対して、コストの上昇が続くと見込まれる。施設総量の適正化やPPP(官民連携)やPFI(プライベートファイナンスイニシアチブ)といった民間資金等の活用、そして、新技術及び新材料の導入等による経費節減及び軽減なども考慮しながら、この総合管理計画の的確な運営に努めてもらいたい。
続いて、令和4年度決算に関する報告書15ページの山村振興ビジョン推進費について伺う。
コロナ禍以前に、長崎県壱岐市におけるSDGsの取組を視察した際に、取組の一環としてワーケーションのための施設整備等を行った結果、壱岐市に全国から人が集まって地域の活性化につながったというワーケーションの可能性を示す好事例を聞いた。
愛知県でも、新型コロナウイルス感染拡大防止を契機とした新たなライフスタイルであるワーケーション等を三河山村地域で推進するために、2021年度にニーズ調査を実施したと聞いている。そして、昨年度は実証実験を実施したとあるが、どのような内容で実施したのか。
【地域振興室長】
三河山間地域ワーケーション推進事業については、三河山間地域において、アフターコロナ時代の新しい働き方として注目されているワーケーションの促進誘致を図るため、2021年度から3年間で実施している。初年度は、企業及び個人に対するワーケーションの実施ニーズや条件等を把握するためのマーケティング調査を行った。
2022年度は、調査結果及び地元町村等へのヒアリング結果等を踏まえ、9月から11月にかけて、実証実験としてモニターツアーを3回実施した。当該ツアーは、調査結果においてワーケーションへの関心が高い傾向にあった中小企業を主な対象として、実施場所は休暇で観光を楽しみつつ、普段の仕事を行う休養活用型のワーケーションに高い関心が示されていたことから、三河山間地域の代表的なキャンプ場や温泉施設を活用した。
また、日程は1泊2日とし、ワークの時間以外に地域のことを知り、関心を持ってもらい、引き続き訪問してもらうきっかけづくりとなるよう、地域に関するワークショップや地元関係者との交流会の時間も設けた。
【日比たけまさ委員】
結果はどうだったのか。また、その成果を今年度の事業にはどのように生かしているのか。
【地域振興室長】
3回のツアーで、名古屋市の企業を中心に、IT関係や建築設計関係と合わせて34人に参加してもらい、アンケートの結果、ツアー全体としては満足したという人の割合が7割を超えるなど、高い評価をもらった。
その一方で、1泊2日ではワークの時間が十分確保できない、宿泊場所とワークスペースは近いほうがよい、データの送受信やウェブ会議実施がスムーズにできる通信環境が必要といった課題が明らかになるとともに、今後実施してみたいワーケーションの形態としては、当初想定していた休養活用型よりも企業間交流や地域貢献、課題解決を目的としたタイプへのニーズが高いことが分かった。
これを踏まえ、今年度はツアーの設定に当たり、期間を2泊3日に拡大し、ワークの時間を十分確保するとともに、宿泊やワークを行う施設を見直し、新たな実施場所を選定した。また、衛星インターネット回線の活用による通信環境の見直し、参加者同士が協働して行う活動や参加者と地元関係者との交流機会を増やすなど、必要な改善、改良を行った上で、9月から10月にかけてツアーを4回実施した。
今後、参加者アンケートを取りまとめ、課題やニーズ等の整理、分析を行った上で、昨年度までの実施結果も踏まえつつ、この地域に適したワーケーションの在り方を検討していく。
三河山間地域内では、市町村や民間事業者においてもワーケーションを推進しようとする動きが出始めている。県としては、この事業の成果を地元市町村としっかり共有することで、こうした動きをより一層活発化させ、三河山間地域におけるワーケーションのさらなる推進につなげていく。
【日比たけまさ委員】
ワーケーションにより、都市部と三河山間地域との人の交流を促してもらいたい。その次の段階としては、ぜひ移住という形につなげてもらいたい。
次に、決算に関する報告書では、首都圏の移住・定住の強化のために、ふるさと回帰支援センターにおいて相談窓口を運営したと記載されている。
そこで、この相談実績について伺う。併せて、窓口の運営で何か課題があれば、その課題と対応についても伺う。
【地域振興室長】
この事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、首都圏等在住者の地方暮らしへの関心が高まり、地方における移住・定住促進に大きな追い風となっていたことから、2021年度に県の移住相談窓口を設置するとともに、専属の移住相談員を配置して、首都圏での移住・定住に関する相談体制の充実を図ったものである。
移住相談件数であるが、2021年度は196件、2022年度は281件と増加している。また、この相談をきっかけに、三河山間地域への移住につながった事例も出てきており、具体的な成果も出始めている。
課題としては、2022年のセンター全体での相談件数は5万2,312件と、44都道府県1政令市が相談窓口を設置している中では、本県の相談件数は相対的に少ない状況である。そのため、まずは、移住先としての愛知県の認知度を高め、相談につなげる必要がある。
今年度から、本県の強みであるバランスの取れた住みやすさをPRする愛知の住みやすさ発信事業を当室で所管することとなったため、これらの事業を連携させ、首都圏における情報発信を強化することで相談件数を増やし、愛知県の移住促進に努める。
【日比たけまさ委員】
まず、三河山間地域の市町村にとって、このワーケーションは、今までと違う新たな地域活性化手段となり得る政策と思っている。事業から得られた結果を地元市町村としっかり共有して、ワーケーション促進を図ってもらいたい。
もう一つ、移住について答弁してもらったが、有楽町にあるふるさと回帰支援センターは、44都道府県1政令市の専属相談員が常駐しているため、移住に関する相談のワンストップサービス拠点となっている一方で、大体の資料がそろうため、地域間での人の奪い合いが起こりうる。そのため、より分かりやすい相談窓口が必要だと考える。
その点で、愛知の住みやすさ発信事業を今年度統合したことは、かなり前進である。労働局が所管しているあいちUIJターン支援センターが新宿にあり、有楽町と新宿に別々でなく、統合も視野に連携強化をしてもらい、さらに愛知県へ人を呼び込むための体制整備に努めてもらいたい。